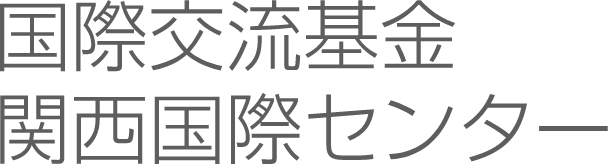令和6年度研修参加者レポート 専門日本語研修(文化・学術専門家)【公募プログラム】
- 専門活動に役立つ魅力的な日本語研修 グエン・キム・ガン(ベトナム)
- 新たな視点の発見:日本での民俗音楽、アイデンティティ、文化交流
サヴァンナ・リヴカ・パウエル(エストニア/アメリカ) - 「日本文化を“舞台裏”から体験する」 レギーナ・ビッヒラ(ドイツ)
専門活動に役立つ魅力的な日本語研修
グエン・キム・ガン(ベトナム)
「専門日本語研修(文化・学術専門家)6か月コース」は、日本に関する研究を進めるために、日本語を活用したい方におすすめのプログラムです。この研修では、専門日本語の向上を目的とし、それぞれの具体的な目標にしっかりと結びついたスケジュールや実践的な授業が行われています。また、先生方のご指導のもと、努力して学ぶことで、プログラム参加前と比べて日本語能力が向上することを確信しています。
総合日本語の授業では、文法・語彙・読解・聴解のスキルを訓練するだけでなく、教材のテーマや生材料を通じて、日本語で意見交換をする機会も得られます。これは、研究に関するセミナーへの参加やプロジェクトの発表などの専門的な活動において、非常に役立つと考えます。また、発表の授業では、インタビューの実施、研究成果の発表、Q&Aなどの具体的な場面を想定し、重要な表現を整理しながら、スムーズに対応できるように練習を行います。その結果、実践的な力が身についていることを実感できます。特に、個別授業はこのプログラムの大きな魅力の一つです。先生方から専門的なサポートを受けながら、自分で設定した目標を実現するための授業であると考えています。個別授業は、プログラムをより自分に合ったものにする貴重な機会であり、自分の学習スタイルに合わせて進められる点も大きなメリットです。そのため、何を達成したいのかをしっかり考え、計画を立て、一歩ずつ実行していくことが大切です。
最後に、日本語で専門分野を深めたいと考えている方にとって、このプログラムは専門的な日本語教育が受けられる最適なものです。6か月間の学びを楽しみながら、プログラムが提供する貴重な機会を最大限に活用し、日本語のスキルを向上させましょう。

新たな視点の発見: 日本での民俗音楽、アイデンティティ、文化交流
サヴァンナ・リヴカ・パウエル(エストニア/アメリカ)
国際交流基金関西国際センターでの学びは、私の博士研究にとって新たなステージの始まりでした。私はエストニアのタルト大学と北海道大学を通じて研究を行っていましたが、この6か月の「専門日本語研修(文化・学術専門家)」に参加することで、研究の視野が広がりました。センターの先生方のご指導のおかげで、文化的な視点が深まり、研究の方向性にも大きな影響を与えました。
この研修には、1~2週間の集中的な研究活動が2回あります。計画を立てて準備をすれば、多くの充実した研究活動を行うことができます。私は学部生の頃に関西を訪れたことがありましたが、博士研究の視点から見るのは初めてでした。私の博士研究は、民俗音楽を通じたマイノリティのアイデンティティ表現について、特にアイヌ文化とユダヤ文化を比較するものです。これまでのフィールドワークでは北海道のアイヌコミュニティを中心に研究をしていましたが、この研修を通じて、横浜のアイヌコミュニティとつながり、大阪のアイヌ文化や多文化共生に関するプロジェクトを知る貴重な機会を得ました。大阪は日本の中でも特に多様性のある都市とされており、文化的多様性をテーマにしたイベントが多く開催されていました。
文化交流は、マイノリティのアイデンティティを支え合うために非常に重要です。フィールドワークの中で、伝統的な歌や踊りを通じた文化交流を行うNPOのイベントに参加しました。そこでは、韓国、うちなー(沖縄)、チベット、ペルーなど、さまざまな文化背景を持つグループがパフォーマンスを行っていました。また、北海道の二風谷(ニブタニ)にいるアイヌの人々の中には、このNPOとつながりのある方もいることがわかりました。多様なネットワークを維持することは、社会の中でマイノリティとして生きる多くの人々にとって大きな意味を持ちます。
また、集中的な研究活動の中で、京都のユダヤ人コミュニティとのつながりを深める機会もありました。ちょうどユダヤ教の祝祭「ハヌカー」の時期だったため、祝祭に参加し、ヘブライ語、英語、日本語で歌われる音楽を通して、多文化的なコミュニティの一面を知ることができました。
研究活動の最後には、北海道を訪れ、アイヌのコミュニティと再会し、北海道大学にも立ち寄りました。浦河町で2日間のワークショップに参加し、地域ごとのアイヌ文化の多様性を尊重する活動に触れることができました。特に印象的だったのは、二風谷のアイヌコミュニティを訪れたことです。ちょうど「第35回シシリムカ・アイヌ文化祭」が開催されており、若者から年配の方まで、伝統的な歌や踊り、語り、叙事詩などを披露していました。また、マオリとの文化交流を通じて学んだ教育手法が活かされ、ジブリ映画の曲をアイヌ語で歌うなど、楽しく学べる場面もありました。
センターに戻り、先生方とフィールドワークを振り返ったことで、新たな視点を得ることができました。もしこの研修がなければ、今回のような貴重な出会いや経験は実現しなかったかもしれません。私の研究を支えてくださった先生方やスタッフの皆様に、心から感謝しています。
「日本文化を“舞台裏”から体験する」
レギーナ・ビッヒラ(ドイツ)
「専門日本語研修(文化・学術専門家)」は、私の専門的な日本語能力を向上させるだけでなく、日本文化への深い理解や興味深い体験の機会を提供してくれました。
このプログラムでは、書道や生け花といった実践的な文化体験に加え、伝統芸能の公演鑑賞も含まれていました。例えば、厳粛な舞踊劇である能、室町時代に生まれたユーモラスな狂言、そして江戸時代の人形浄瑠璃である文楽など、多様な芸能に触れることができました。特に文楽は、大阪発祥の芸能でありながら、日本全国で広く知られているため、非常に興味深く鑑賞しました。観光客としてこれらの公演を観るだけでは、ストーリーや登場人物の所作の意味を理解するのは難しいかもしれません。しかし、研修では、各芸能の背景やストーリーの解説があり、重要な所作の意味についても詳しく説明を受けたため、より深く楽しむことができました。さらに、文楽の公演後には、プロの人形遣いによる「舞台裏」レクチャーがあり、文楽の演技の難しさについて学ぶとともに、実際に(とても重い!)文楽人形を動かす貴重な体験をすることもできました。
また、日本の文化や社会をより深く理解する機会として、小学校訪問もありました。これは、通常、外国人観光客には許可されない貴重な体験です。私たちの多くは、日本の学校についてマンガやアニメ、ドラマを通じて知識を得ていましたが、実際に訪れてみると、その印象は大きく変わりました。私たちは、フレンドリーな校長先生に迎えられ、そして校舎内を吹き抜ける冷たい風(感染症対策のためとのこと)に驚きました。しかし、教室内は暖房が効いており、快適な環境で子どもたちに自国や研究について紹介することができました。まず、私たちは母国語で自己紹介を行い、1・2年生と一緒にスポーツ活動を楽しみました。子どもたちは、新しい言語で言葉を発することに興味津々で、とても楽しんでいる様子でした。その後、3・4年生には私たちの出身国について紹介しました。彼らの多くはまだ海外に行ったことがなく、「外国とはどんなところなのか?」と熱心に耳を傾けていました。休み時間には、積極的に私たちに質問をしに来て、仲良くなろうとしてくれる子もいました。最後の授業では、5・6年生に向けて私たちの研究内容を説明しました。彼らは、外国人である私たちが流暢に日本語を話すことに驚き、興味を持って聞いてくれました。特に、心身に障害のある子どもたちへの支援に学校全体で取り組んでいることに深く感銘を受けました。また、日本の学校では幼い頃から厳しい制服の規則があるという先入観を持っていましたが、実際には子どもたちが個々のニーズに応じて制服をアレンジできることを知り、驚きました。全体を通して、日本社会に関心のある人なら誰でも楽しめる、非常に貴重で思い出に残る経験でした。
さらに、ホームビジット・プログラムも非常に充実していました。二人一組のグループで、まずホストファミリーと電話で連絡を取り(これは日本語の練習にもなりました!)、その後、ホストファミリーの家で夕食をご馳走になりました。私とクラスメイトは、寿司、おでん、お好み焼き、さらにはベジタリアン向けの料理まで、種類も量も豊富な日本食を存分に楽しみました。私たちはホストと素晴らしい関係を築くことができました。彼女は何度もセンターを訪れ、私や友人たちを自宅に招待してくれました。私たちは今後も連絡を取り合う予定で、彼女も「いつかドイツに遊びに行くわね」と約束してくれました。