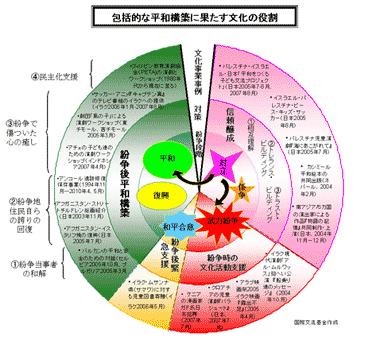小冊子出版紹介 「文化が創る国際平和:平和構築と文化」 The Roles of Cultural Activities in Peacebuilding
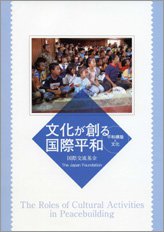
国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)は、その使命のひとつとして文化交流すなわち日本文化の紹介や日本語教育を鋭意進めていますが、あわせて文化交流を通じて日本外交や平和の創造・構築に貢献することも求められています。
現在では、20世紀のように戦争がない状態が、即平和を意味するわけではありません。戦争に到らない段階でも様々なリスクが発生し、平和と安全の方程式は冷戦時代とは異なり、複雑になりました。例えばバルカン、アフリカ諸国、東チモールなどでは内戦型紛争が発生しています。さらに紛争以外にもテロをはじめとして、国内騒乱など様々な事象が人々の平和と安寧を損なっています。しかも一旦和平合意が成立し、紛争が収束しても約半分が再発しているのが現状です。
いまや紛争当事者間に和平合意が成立しても、平和は必ずしも約束されません。紛争直後の元紛争地では軍隊による平和維持、また開発援助による上下水道、道路、橋、学校、市場、病院、住宅などの復興がまず必要なことはいうまでもありません。しかし軍事力と経済援助だけでは、不十分です。元紛争地の人々の心に平和が戻らなければ、紛争により受けた痛手から回復し、敵対したグループと和解し、自らの将来に夢を持てない限り、真の持続的な平和への道は決して開かれません。そこに文化交流が果たす役割があります。これは紛争前の敵対グループ間の意思疎通、信頼醸成についても同様です。民族や宗教等を異にするグループが対立し、小競り合いを繰り返している段階では、流血の惨事が発生する前にお互いが話し合い、共通体験をもち、お互いを理解し、尊重することは容易ではありません。特に政治的な対話は難しいことも少なくありませんが、文化を触媒とファシリテーターにすることで、同じ考え方を共有できなくともお互いの文化や歴史を尊重することはできるはずです。
本冊子は、国際交流基金の最近の文化交流事業例の中から元紛争地の人々、或いは長年対立してきた人々の間の文化交流を推進した事例のうち、包括的な平和構築に寄与したと思われる事例をもとに平和構築に果たす文化交流の役割をグラフに示すように紛争段階に分けて考察したものです。まだ、この研究は緒についたばかりですが、平和に果たす文化の具体的な役割を考えるご参考になれば幸いです。
| 本書の構成 |
|---|
巻末資料 国際交流基金の文化を通じた包括的平和構築関連事業例 |
国際交流基金 総務部総務課
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-1
電話: 03-5369-6051 FAX: 03-5369-6031