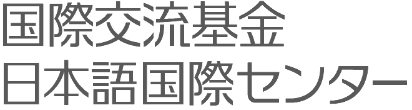2010年度上半期 調査研究プロジェクト
ノンネイティブ日本語教師の漢字学習における困難点の整理
| 計画者 | 濱川祐紀代 |
|---|---|
| プロジェクト参加者 | 二瓶知子(専任講師) |
| 外部協力者 | 関麻由美(客員講師) ウラムバヤル ツェツェグドラム(日本言語文化研究プログラム) |
| 日程 |
開始2010年5月 ~ 終了2011年3月
|
目的と概要
漢字学習に難しさを感じる日本語学習者は多いが、具体的に何が難しいのかについて答えられる教師は多くない。また、その難しさに対してどのような学習を行えばいいのかといった具体的なアドバイスのできる教師も多くないだろう。そこで、直感や経験を頼りにするだけでなく、調査結果や理論に基づいたアドバイスができるよう、漢字学習の困難点や難しさについて明らかにしたい。先行研究には、日本語学習者の漢字学習における困難点に関するものがいくつか見られるが、ノンネイティブ日本語教師を対象とした調査は管見の限り見られない。そこで、本プロジェクトでは、当センターが主な対象とするノンネイティブ日本語教師に着目し、「ノンネイティブ日本語教師の漢字学習上の困難点」を明らかにするための研究の端緒として、漢字テストの解答を用いた誤答分析を行い、誤答の傾向を明らかにした。しかしこの誤答傾向は対象者全体のものであり、レベル別特徴を明らかにすることができていない。また漢字テストの誤答は、漢字学習の困難点の一部でしかない。今後は、これらを明らかにすることから着手し、困難点全体の解明につなげたい。
成果の概要
2009年度長期研修(6ヶ月)の開始時・終了時に行った漢字テストの解答(コピー)を用い、誤答分析を行った。ここでは、長期研修の研修参加者44名のうち、プレイスメントテストでBコースと判定された16カ国22名分(非漢字系)について報告する。漢字テストは読みと書きをあわせて100点であり、読みは漢字部分に下線が引いてあり、かなで回答するもの、書きは漢字部分が空欄になっており、かなで書かれた読みを見て漢字を書きこむものである。また、総合初等教育研究所(2005)の観点を援用し、読みテストは4種類13項目(表1)、書きテストは4種類15項目(表2)を用いて、誤答を分類・分析した。
| 誤答の種類 | 下位項目 |
|---|---|
| 1.字音誤用 | ①音訓の取り違えによる誤用 |
| ②音または訓の別の読み方の取り違えによる誤用 | |
| ③類似字音の連想による誤用 | |
| 2.字形誤用 | ④字形類似の漢字の混同による誤用 |
| ⑤偏旁の一部からの連想による誤用 | |
| 3.字義誤用 | ⑥類義語の連想による誤用 |
| ⑦反意語の連想による誤用 | |
| ⑧熟語の意味から連想した誤用 | |
| 4.その他 | ⑨送り仮名からの類推による誤用 |
| ⑩文脈からの類推による誤用 | |
| ⑪漢語を構成する片方の字からの類推による誤用 | |
| ⑫正しい表記ができないことによる誤用 | |
| ⑬漢語の停滞・転倒による誤用・その他 |
| 誤答の種類 | 下位項目 |
|---|---|
| 1.字音誤用 | ①同訓異字(義)の当て字 |
| ②同音異字(義)の当て字 | |
| ③発音的誤用による当て字 | |
| ④音の類似による誤用 | |
| ⑫読み方が同じまたは似ていて、意味の類似した漢字の誤り | |
| 2.字形誤用 | ⑤字形の不確実な記憶による誤り |
| ⑥字形類似の誤用 | |
| ⑦同音で字形類似の誤用 | |
| ⑧偏旁の転位 | |
| ⑨省略漢字・旧字 | |
| ⑩書写的な不注意による誤り | |
| 3.字義誤用 | ⑪類義語や字義の連想による誤り |
| ⑮反対語の想起による誤り | |
| 4.その他 | ⑬漢語の停滞・転倒による誤り・その他 |
| ⑭漢語の連想による誤字 |
読みテスト・書きテストの誤答のうち、出現率の上位3位は表3・4の通りである。
| 下位項目 | % | |
|---|---|---|
| 1位 | ③類似字音の連想 | 24 |
| 2位 | ⑬漢語の停滞・転倒、その他 | 17.3 |
| 3位 | ①音訓の取り違え | 13.3 |
| 下位項目 | % | |
|---|---|---|
| 1位 | ⑥字形類似 | 33.5 |
| 2位 | ③発音的類似 | 25.1 |
| 3位 | ②同音異字(義) | 11.9 |
読みテストにおいては、音訓の情報が増えることによって混同し、誤答となってしまう、類似した字形の漢字と混同し読み間違えてしまうといった傾向が見られた。書きテストにおいては、類似した読み方を持つ漢字と混同してしまったり、類似した字形の別の漢字と混同してしまったりすることが見られた。
また、日本人児童の誤答出現率(総合初等教育研究所2005)と比較してみると、どの学年のものとも異なる傾向が見られた。したがって、日本語母語話者の漢字学習経験に頼った漢字指導には、注意が必要であることがわかった。
今後は、同データから、日本語能力や漢字力によって、出現する誤答の種類が異なるのかなど、さらに考察を続けたい。また漢字テストの誤答は、漢字学習の困難点の一部でしかないため、今後は、複数の観点から困難点を明らかにし、困難点全体の解明につなげていきたい。
- 参考文献
-
- 総合初等教育研究所(2005)『総教研・教育調査シリーズ「教育漢字の読み・書きの習得に関する調査と研究」第3回調査2003年実施』