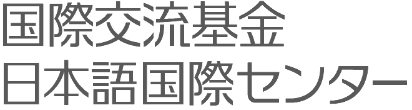第21回海外日本語教育研究会
公開シンポジウム「21世紀の人材育成をめざす東南アジア5か国の中等教育における日本語教育-各国の教育文書から見える教育のパラダイムシフト-」
国際交流基金日本語国際センターは、インドネシア・タイ・フィリピン・ベトナム・マレーシアの中等教育の教育文書についての調査の結果をまとめ、報告書『21世紀の人材育成をめざす東南アジア5か国の中等教育における日本語教育-各国教育文書から見える教育のパラダイムシフト-』 (和文・英文)を2015年9月に刊行し、国際交流基金ウェブサイトでも紹介しました。この報告書の内容をテーマとして、2016年1月30日、120名以上の参加者を得て、日本語国際センター佐藤ホールにて公開シンポジウムが開催されました。シンポジウムで配布された資料及びパネルディスカッションの記録は、報告下部からダウンロードできます。
【基調講演】では、国立教育政策研究所の松尾知明総括研究官 より、日本の学習指導要領の改訂にあたり行われた、世界各国の教育改革に関する調査から得られた知見をもとに、諸外国の例を引きつつコンピテンシーや21世紀型スキルなどの新しい教育の潮流を概観する報告が行われました。その後、【調査報告】として、東南アジア5か国の教育文書に見られる新しい資質・能力観といった共通点と各国の独自の文脈を活かした特徴について、日本語国際センター専任講師の大舩ちさと・尾関史の両名が報告しました。

松尾氏による基調講演
シンポジウム後半は【事例紹介】として、教育現場でどのように新しい資質・能力観の育成を図るかという点から2つの発表がありました。まず、タイ・カランヤニー中等学校教諭のティーラット・ロムスィー氏 は、8か国の高校生と教師が参加して行われた「タイ国際キャンプ」について報告しました。次に、東京経営短期大学専任講師(元国際交流基金派遣日本語専門家)の上野美香氏 と、インドネシア・ブキティンギ第5国立高校教諭のデヴィ・クマラ・トゥリスニ氏からは、インドネシアの「2013年カリキュラム」で提案されている科学的アプローチという方法を盛り込んだ新しい教科書とその利用についての紹介がありました。

ロムスィー氏による報告

上野氏とトゥリスニ氏による報告
【事例紹介】に続く【パネルディスカッション】 は、松尾氏、ロムスィー氏、上野氏のほかに、当センターの坪山由美子専任講師、中野佳代子元国際交流基金参与の5名を登壇者に迎え、古川嘉子専任講師の司会で進めました。ディスカッション前半では、生徒たちの資質・能力を育てる教師の研修に焦点をあてて、登壇者からは教師に求められるもの、研修の方法や留意点などについての発言がありました。後半は、中野氏 から今回の調査で見えてきたことや、今後の中等教育での日本語教育の課題や可能性についてのまとめがあり、最後に、松尾氏より、シンポジウム全体を締めくくって教育としての日本語という視点の重要性について提言をいただきました。パネルディスカッションの討議の概要は、下部よりダウンロードいただけます。

パネルディスカッションの様子

中野氏
当日は、日本語国際センター図書館 でも、今回の調査対象である5か国のカリキュラムや教材、そして21世紀型スキルやOECDのキー・コンピテンシーに関する参考文献の展示を行い、休憩時などに、多くの方の閲覧に供しました。

図書館での資料展示の様子
当日のプログラムと資料
- 基調講演 「諸外国の教育改革に見る21世紀型の資質・能力と学びのイノベーション」【PDF:776KB】
松尾知明 (国立教育政策研究所 初等中等教育研究部総括研究官) - 調査報告 「東南アジア5か国の中等教育における日本語教育調査」【PDF:276KB】
大舩ちさと、尾関史 (日本語国際センター専任講師) - 事例紹介1 「タイの現場からわかること-国際キャンプでの試み」【PDF:598KB】
ティーラット・ロムスィー(タイ・カンラヤニー中等学校教員) - 事例紹介2 「インドネシアの「2013年カリキュラム」と高校日本語教材作成」【PDF:373KB】
上野美香(東京経営短期大学専任講師 / 元国際交流基金インドネシア派遣日本語専門家)
デヴィ・クマラ・トゥリスニ(インドネシア・ブキティンギ第5国立高校教諭) - パネルディスカッション【PDF:208KB】
登壇者:松尾知明、ティーラット・ロムスィー、上野美香(以上、発表者)、坪山由美子 (日本語国際センター専任講師)
中野佳代子(元日本語国際センター参与)
司会進行:古川嘉子 (日本語国際センター専任講師主任)
お問い合わせ
国際交流基金日本語国際センター
教師研修チーム
Eメール : urawa@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角@マークに変更してください)