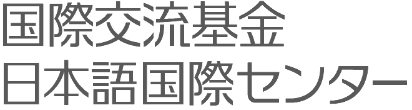令和7(2025)年度外国人材受入れのための日本語教師研修教授法(第1回) 研修参加者の声
(修了式での、ご本人による日本語のスピーチを一部編集しました。)

アルニさん(バジュラチャルエ アルニ マイヤ/BAJRACHARYA ARNI MAIYA/ネパール/JLECC日本語教育文化センター)

ナマステ、おはようございます。ただいまご紹介いただきましたネパールのアルニです。
本日、「令和7年度外国人材受入れのための日本語教師研修(教授法・第1回)」の代表として、スピーチができることを大変光栄に思っております。
この会場で開講式を行ったのは、つい昨日のことのようです。時間が経つのは速く、あっという間に研修が終了することになり信じられないほどです。6月3日から本日までの短い期間の研修でしたが、国を意識せず、10か国の33名が楽しく、良い環境でそれぞれの仕事の目標に向けて集中して勉強できました。これは言うまでもなく、素晴らしい研修を提供してくださった国際交流基金(JF)日本語国際センターの先生方、職員の皆様のおかげです。
このプログラムには、日本語教育だけでなくさまざまな授業がありました。来日前の事前課題からはじまり、授業オリエンテーション、研修の目標設定、『いろどり 生活の日本語』の教え方、日本の社会と文化、関係者訪問、介護施設訪問、『JFT-Basic』と『いろどり 日本語オンラインコース』/ひきだすにほんご「スアンちゃん」、メンタルヘルス、ビジターセッションもありました。最後は模擬授業、そして帰国後の計画の発表がありました。そのほかにも限られた時間内に豊富な教材とさまざまなグループディスカッションを提供してくださいました。それぞれの活動にかける時間の設定も細かく計画されていて素晴らしいと思いました。文化体験、東京見学といった教室の外での活動も充実するように工夫されていることには大変感動しました。そして、それぞれの活動の後に振り返りをすることも非常に良かったです。
常に大変優しく、親切に励ましてくださった先生方の明るい笑顔は一生忘れません。もう言葉では表現できないほどの気持ちで一杯です。想像以上のたくさんのことを学べる良い機会を与えていただきまして、心より深く感謝を申し上げます。
日本のことわざに「同じ釜(かま)の飯を食う」と言う言葉があります。お陰様で、私達33名の国や所属機関のお互いの情報が共有でき、悩みには共通点が多いことにも気が付く大変貴重な機会になりました。また、娯楽室でカラオケをしたり、卓球やテニスをしたり、たくさん笑ったり、お互い冗談を言ったり、週末は一緒に買い物や、日本の文化にもっと触れるために観光したり、外食したりして、非常に充実した時間でした。本日この場で、先生方、センターの皆様、33名の仲間たちとの別れはつらいですが、帰国後の皆さんの活動を、所属機関や学習者たちが首を長くして待っていると思います。これからも、日本語国際センターの皆様方、仲間の皆さんくれぐれもご健康に気を付けながら、ますます活躍されることを心よりお祈りしております。
ここで出会った皆様との関係はこれで終わりではなく、これからはじまりですね。今後も通信メディアを通して、お互いの悩みや課題、そして楽しいこともお話ししましょう。そして、最終的にゴールであるCan-doを確認することは、私たちの日常生活にも活かすこともできますね。一日の終わりにCan-doをチェックするのも良いのではないでしょうか。非常に良い勉強ができました。
さて、研修者の皆さん、Can-do 達成できましたか。
ご清聴ありがとうございました。ダニヤバード
お問い合わせ
国際交流基金(JF)日本語国際センター
教師研修チーム
電話:048-834-1181 ファックス:048-834-1170
Eメール:urawakenshu@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください。)