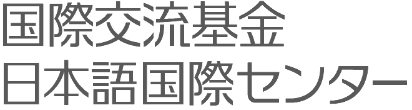令和7(2025)年度外国人材受入れのための日本語教師研修(日本語)
研修参加者の声
(修了式での、ご本人による日本語のスピーチを一部編集しました。)
1クラス
ミラさん(シラミズ ミラルナ サラザル/ SHIRAMIZU MIRALUNA SALAZAR/フィリピン/
LIPA CITY COLLEGES)

皆様こんにちは。1クラスのミラです。
5週間長かったようで、短かったです。
1クラス研修生を代表してひとことごあいさつを申し上げます。
はじめに、国際交流基金日本語国際センターで、学ぶ機会をいただき、心より感謝いたします。
ここでの研修は、私たち、教師にとって大切なステップでした。日本語の学習だけでなく、文化体験、ホームビジットや、お祭りでの踊りは、わすれられない経験となりました。スタッフの皆様、健康的な食事を用意してくださった食堂の方々、いつも助けて下さってありがとうございます。また、先生方の熱心なご指導と宿題のお陰で学びを深めることができました。ご支援、心より感謝申し上げます。
この研修は、私たちにとって大きな成果となりました。ここで学んだことは、必ず学生たちに伝えます。国連のSDGsの4番の「質の高い教育をみんなに」や17番の「パートナーシップで目標を達成しよう」という考えにもつながると信じております。
異なる文化を持つ研修生たちが集まり、学び、笑いあったこの経験は永遠の宝物です。
これからもIrodoriの精神を世界に広げ、言語と文化とお互いの理解の架け橋となってまいります。
2クラス
マムンさん(アル マムン アブドッラ/AL -MAMUN ABDULLAH/バングラデシュ /
日本バングラデシュ文化会)

皆さま、こんにちは。マムンと申します。バングラデシュ出身です。よろしくお願いいたします。
本日は国際交流基金(JF)からこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。バングラデシュからこの日本語教師研修プログラムに参加することができました。これは私にとって、とても貴重で忘れられない経験となりました。
皆さん、バングラデシュはどんな国だと思いますか?実は日本の3分の1くらいの大きさで、人口は日本の約1.5倍です。そんな国でも、去年行なわれたJLPTを受験した学習者は9,000人以上、約1万人でした。この数は毎年増えています。そのため、日本語学校も増えています。しかし、このように熱心な学生たちに十分に日本語を教えられる先生はまだ少ないのが現状です。
ですから、JFがこのような研修を開催してくださったことは、私たちのような国々にとって大きな助けになると思います。バングラデシュだけでなく、インドネシア、ベトナム、フィリピン、インド、スリランカ、ネパールなど東南アジアと南アジアのこれらの国々は経験豊富な教師を輩出すると思います。
これからもこのような研修をもっと頻繁に開催してくださることを願っています。このプログラムでは、日本人の先生方から日本で生活する時に必要な日本語を教えて頂きました。私たちの日本語コミュニケーションの力は高くなり、日本のどこへいっても自信をもって日本語でコミュニケーション出来るようになりました。また日本語の授業では日本語教育のさまざまな教授法や指導の工夫についても学ぶことができました。具体的には、効果的な授業の進め方、学習者のモチベーションを高める方法、そして文化を取り入れた授業の工夫などを教えていただきました。特にロールプレイやグループワークなど、学習者が主体的に参加できる活動がとても印象に残っています。
私はこの研修を通じて、教師にとって大切なのはただ日本語を教えることではなく、学習者が楽しく、意欲的に学べる環境をつくることだと強く感じました。
最後に、このような素晴らしい機会を与えてくださった国際交流基金日本語国際センターの先生方に、心より感謝申し上げます。そして、この1か月間、さまざまな国の先生方と一緒に研修に参加し、仲良くなれたこともとても嬉しかったです。今日でお別れするのは少し寂しいですが、でも皆さんと一緒にグローバルネットワークが出来上がりましたのでそれはいい思い出として心に大切に持ち帰りたいと思います。 皆さま、本当にありがとうございました。
3クラス
デシーさん(デシー アマリア プトリ エル/DESY AMALIA PUTRI R/インドネシア/
オリオン ハルモニ マンダラ(株式会社OHM))

皆様、こんにちは。3クラスを代表してスピーチさせていただきます。デシーと申します。どうぞよろしくお願いします。
この修了式にあたり、まずは、このような貴重な学びの機会を設けてくださった国際交流基金日本語国際センターの皆様に、心より御礼申し上げます。
また、豊富な知識と経験をもとに丁寧にご指導くださった先生方、そして研修を陰ながら支えてくださったスタッフの皆様にも、深く感謝いたします。
そして、最後まで共に頑張ってきた30人の参加者の皆さんにも、ありがとうの気持ちを伝えたいと思います。
私たちは異なる国々から集まりましたが、この5週間で一つのチームとなり、まるで家族のような存在になれたと感じています。一緒に時間を過ごし、食堂でおいしい食事を楽しんだり、お互いの国の文化や考え方について語り合ったり、たくさん笑い合いました。週末には、共に日本のお祭りを見学する機会にも恵まれました。たくさんの思い出を作ることができて、皆さんも、この時間を十分に楽しみましたよね? センターでの文化体験では、ほかにもさまざまな体験をしましたが、私は、特にホームビジットが印象に残っています。日本の家庭で一日を過ごすことで、日本人の生活をより身近に感じることができました。 そして何より3クラスでは担当の先生方から本当に多くのことを学びました。自分の国ではなかなか得られない貴重な学びと知識がたくさんありました。素晴らしい先生方に出会えたことを、心から嬉しく思っています。先生方のわかりやすく、私にとって新しい教え方のおかげで、私たち3クラスの仲間たちは、楽しみながら、でも深く理解して日本語を改めて学ぶことができました。
私たちは、自分の国では、日本語を教える立場にあり、この研修に来るまで、ある程度、自分の知識は十分だと思っていたかもしれません。しかし、この研修を通して、まだ学ぶべきことが多くあると強く感じました。それは学生のためでもあり、自分自身の成長のためでもあります。
3クラスで学びはじめたとき、周りの皆が日本語で自然に話していて、私も同じように話せていると思っていました。しかし授業を重ねるうちに、それが少し違うことに気づきました。もし私たちの日本語の力を一本の木にたとえるなら、私たちが持っている語彙や文法の知識だけでは、その日本語の木は、まだ土に隠れた「根」の部分に留まっているのだと思います。この研修を通して、日本語をもっと深く理解しながらも、実際のさまざまな生活の場面で使いこなし、自信を持ってコミュニケーションができるようになることが大切だと感じるようになりました。
もちろん、それは簡単なことではありません。間違えることへの不安や、自信のなさを感じる場面も多くありました。でも、この研修のおかげで、私たちの「日本語の木」は、少しずつ芽を出し、枝を伸ばし、成長し始めたと思います。
これからも、水を注ぐように学びを続け、太陽の光のような経験を重ねながら、より高く、より強く成長していきたいと思います。やがて、私たちの「日本語の木」が花を咲かせ、日本語を学ぶ学生たちにとっての木陰となれるように願っています。そして、この研修で得たことを、これからも大切にしていきたいと思います。 本日は誠にありがとうございました。

外国人材(日本語)集合写真
お問い合わせ
国際交流基金(JF)日本語国際センター
教師研修チーム
電話:048-834-1181 ファックス:048-834-1170
E-mail:urawakenshu@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください。)