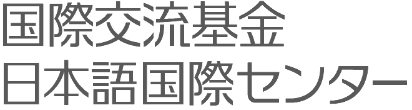夷石 寿賀子(いせき すがこ)ISEKI Sugako
学歴
麗澤大学大学院 言語教育研究科 日本語教育学専攻 博士課程後期 単位取得退学
おもな教授歴
- 双葉外語学校 非常勤講師
- 国際交流基金 パリ日本文化会館 日本語教育指導助手
- フランス パリ・ディドロ(第七)大学 講師
- ドイツ マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク 講師
- 神奈川大学 非常勤講師
- 青山学院大学 非常勤教師 など
執筆論文、著書、発表など
- 伊藤由希子・夷石寿賀子・池田香菜子・菊岡由夏(2024)「B1レベルのJF Can-do作成 -課題遂行を目標とした教育実践の支援を目的として-」『国際交流基金日本語教育論集』20、1-14
- 篠原亜紀・夷石寿賀子(2023)「CBT方式による日本語スピーキングテストの試作と試行―テストの品質と項目数の検証―」『国際交流基金日本語教育紀要』19、1-14
- 篠原亜紀・夷石寿賀子・石田華奈子・李文鑫(2021)「CBT 方式によるスピーキングテストの現状」『国際交流基金日本語教育紀要』17、227-238
- 夷石寿賀子(2017)「中等教育日本語初学者向けアプリ『エリンと挑戦!にほんごテスト』の開発」(ポスター発表),2017年度日本語教育学会秋季大会
- 夷石寿賀子(2017)「日本語初学者向け教材開発におけるターゲットの調査・分析」,日本教育工学会第33 回全国大会
- 夷石寿賀子、川上ゆか(2017)「訪日インバウンド向け日本語教材の「広島観光Can-doリスト」と「言語使用場面」」 (ポスター発表),EAJS2017 Conference in Lisbon
- 夷石寿賀子(2012)「日本語教師とE-Learning-MoodleとILIASでのコース作成の実践と課題―」,第18回ドイツ語圏大学日本語教育研究会シンポジウム
- 夷石寿賀子(2010)「パリ・ディドロ大学における日本語e-Learningについて」,E-Learning in Deutschland und Europa
- 夷石寿賀子、新井優子、ジロー岩内佳代子、小間井麗、中島晶子、大島弘子(2009)「Moodle を利用した日本語コースデザインについて―オープンリソースシステムの利用と可能性―」,第14回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム
- 夷石寿賀子(2008)「日本語教師研修を考える ―パリ日本文化会館の日本語教師のための研修会を例として―」,第10回フランス日本語教育シンポジウム
- 夷石寿賀子、北條淳子(2007)「欧州における日本語教師研修会開催の意義と課題―欧州日本語教師研修会報告―」 (ポスター発表),第12回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム
- 夷石寿賀子(2007)「日本語コーパスの現状と将来 ―言語研究,日本語教育に向けて―」,第9回フランス日本語教育シンポジウム
- 千葉庄寿、夷石寿賀子、陳君慧(2006)「『青空文庫』を言語コーパスとして使おう―メタデータ構築による歴史的・社会言語学的研究への応用の試み―」(ポスター発表),言語処理学会第12回年次大会
- 夷石寿賀子(2005)「日本語の接触動詞における構文交替について―接触動詞「さわる」「ふれる」を中心に―」,『日語研究』31,韓国日本語教育学会
- 夷石寿賀子(2004)「日本語コーパスを利用した格助詞の研究―接触動詞における格助詞の交替を中心として―」,韓国日本語教育学会 第41回国際学術大会
- 夷石寿賀子(2003)「鳥取方言のカラ方言について」,『言語と文明』1,麗澤大学大学院言語教育研究科
所属学会
ヨーロッパ日本語教師会、英語コーパス学会、日本教育工学会、日本語教育学会
ひとこと
「話す」ではなく「伝わる」「伝える」とは何だろうという壁に前職でぶつかり、紆余曲折を経て、気がつけば日本語教育の世界にやってきました。元々文法が専門で、コーパスに基づいた研究も行っていましたが、近年は教材制作を主としています。また欧州で教えていた経験からCEFR、JF日本語教育スタンダードにも関心があります。
About Us 日本語国際センターについて