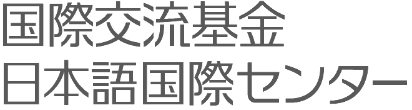日本語国際センター日本語教育専門員の仕事
1. 教師研修の仕事
教師研修の概要
日本語国際センター(NC)では、世界各地から主に外国人日本語教師を招聘して研修を実施しています。研修期間は、短期の研修は10日間から2か月程度、長期の研修は約6か月です。
多様な国・地域からの教師が共に学ぶ研修としては、教師としての日本語運用力の向上を目的とした日本語研修、教授能力の向上を目的とした教授法総合研修、比較的教授経験の短い若手日本語教師を対象にした基礎研修などがあります。韓国や中国など特定の国の中等教育機関の教師を対象とした国別研修や、在留資格「特定技能」での来日を希望する学習者に日本語を教える教師を対象とした研修も実施しています。他の団体との共催や受託による教師研修も行っています。
NCの教師研修の特徴は、日本語教師としての今までの実践をふり返り、他の教師との協働を通して、自律的に学ぶための研修であることです。
日本語教育専門員の業務内容
教師研修を担当する日本語教育専門員は、研修ごとに、参加する教師の教授環境・教授経験・ニーズ・日本語運用力に合わせた研修目標を設定し、カリキュラムやシラバスを作成しています。各国・地域の教育事情や日本語授業の実際に沿った研修を実施するため、研修をデザインし授業を担当する日本語教育専門員は、世界各地の日本語教育の動向にアンテナを張り、研修内容と自身の教育能力をふり返ることが不可欠になります。
教師研修に携わることで、日本語教育専門員は、世界の日本語教育について広く深く知る機会を得ることができます。そして、研修業務から得られた知見をもとに試行錯誤を重ね、各地の日本語教育の後方支援に関われるよう努力を続けています。
2. 教材開発の仕事
教材開発の概要
NCでは、日本語教育の多様なニーズに対応し、日本語教師の教育実践や学習者のより良い学びを支援するために、さまざまな開発業務も行っています。
「JF日本語教育スタンダード」(JFS)は、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を参考に開発した日本語の教え方・学び方・評価のし方を考えるための参照ツールです。JFSの考え方を現場の実践に活用していただくため、Can-doの開発とデータベースの公開(「みんなのCan-doサイト」)、JFS準拠教材である『まるごと 日本のことばと文化』と『いろどり 生活の日本語』の制作、JFSに基づいた評価方法(ロールプレイテスト・産出の評価事例など)の開発と普及にも取り組んでいます。
また、教材用素材や授業アイデアなどを教師向けに提供する「みんなの教材サイト」、中等教育向け映像教材「エリンが挑戦!にほんごできます。」の動画を中心とした「エリンが挑戦!にほんごできます。」コンテンツライブラリーなどのサイトの開発運営も行っています。日本の社会生活について学ぶ日本語学習番組「ひきだすにほんご Activate your Japanese!」もNHKエデュケーショナルと共同制作し、ひきだすにほんご Activate your Japanese!コンテンツライブラリーで番組の動画と資料・授業アイデアを提供しています。
そのほか、WEBマガジン「日本語教育通信」や『国際交流基金日本語教育論集』で、世界各地の日本語教育に関する情報発信を行っています。
日本語教育専門員の業務内容
教材開発に携わる日本語教育専門員は、国内外の日本語教師や学習者に求められている教材について情報収集と分析を行い、職員も含めたチームで教材を制作します。教材開発の仕事では、イラストレーター、サイト開発会社のシステムエンジニア、出版社の編集者、音声収録のための声優やスタジオエンジニアといった幅広い業種の方々と一緒に働く機会が得られます。動画教材を制作するときは、俳優の選定に関わったりロケに立ち会ったりすることもあります。
教材は完成したら終わりではなく、多くの現場で使っていただくため、開発理念や具体的な使い方などについてセミナーを実施して広報したり、実際に使ってくださっている現場の方々からの問い合わせに対応したりすることも、大事な教材開発の仕事です。
3. 海外での仕事
日本語教育専門員は、派遣専門家(注)として海外に赴任して、その国・地域の日本語教育支援に直接携わり、その経験を国際交流基金(JF)の日本語事業全体に還元することも期待されています。派遣専門家は、派遣先の日本語教育の現状・ニーズを的確に把握したうえで、関係者と協力しながら、日本語教育の定着と自立化の促進を目指した支援を行います。派遣専門家の業務は、日本語教師の育成、カリキュラムや教材の制作や助言、教師間ネットワークの促進支援、日本語講座の授業運営など、多岐に亘ります。(NC)の研修に参加した教師とのネットワークは、派遣先での仕事の大きな力になります。また、自身が海外の現場に赴任することで、現地の日本語教育の発展や充実を直に感じることができます。
注:JFの海外派遣専門家(日本語上級専門家・日本語専門家)の業務については、次の動画をご覧ください。日本語で世界をつなぐ ~国際交流基金 日本語専門家~ (youtube.com)
4. 日本語教育専門員に求められるもの
日本語国際センターの日本語教育専門員の仕事は、世界各地の日本語教育を支援することが目的です。そのため、多様な現場の状況や教師たちの現状・課題を理解し、課題解決するための専門性が必要です。また、教師研修も教材開発もチーム体制で進められることがほとんどですので、建設的に議論しながら業務に当たることのできる協働力が不可欠です。