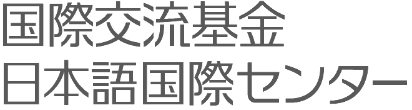2005年度下半期 調査研究プロジェクト 「対国内中等教育機関交流」プロジェクト(報告書)
| 計画者 | 木谷直之、島田徳子、前田綱紀、坪山由美子、長坂水晶、押尾和美 |
|---|---|
| プロジェクト参加者 | 上記と同じ |
| 外部協力者 | なし |
| 日程 | 開始2005年10月~終了2006年9月 |
目的と概要
本研究は、「研修生と国内の中等教育関係者との交流を通した相互理解の進め方を模索すること」を目的としている。2002年に着手し、今年は4年目であった。これまでの流れを概説する。
1年目は、本研究プロジェクトメンバーが中心となり、短期研修(中国中等、タイ、短期春、米加英、短期夏、韓国の6研修)で交流を実施した。その過程で、交流には「目的(情報の授受や教材作成)」「訪問形態」「中等機関側の対応」「センターのとり組み枠」など、様々な要素が関与することが明らかになり、その結果は研究会での発表、紀要への執筆等で報告した。
2年目は、交流の形態の定型化を目指し、研修担当講師を本研究プロジェクトメンバーが支援する形で交流を企画し、実施した研修の数は8研修に増えた。また、2004年1月には、海外日本語教育研究会のテーマとしてとり上げられ、それまでの研究成果や交流の成果を報告することができた。
3年目は、これまでの実践とその成果を基礎とし6研修で交流した。そのうち、中高生ボランティアと外国人日本語教師の「素材収集型交流活動」(大洋州と韓国研修)に焦点を当て、データを収集・分析し、その考察結果を異文化間教育学会で発表し、基金紀要でも報告した。
今年度、プロジェクトの主要目標としていたことは、次の点であった。
- (1) 「素材収集から教材化」までの作業過程に中高生ボランティアが関われる機会を増やし、参加者の中に起こる意識変化等に焦点を当てた研究を行い、その成果を研究会や、論集への執筆で報告する。
- (2) 研修生の帰国後、交流成果をどう活用しているかにつき、これまでも情報収集に努めてきたが、その方法をより具体化・精緻化し、フォローアップ調査を充実させる。
- (3) 国際交流基金本部と連携した形での新規の国際交流事業の提言を模索する
成果の概要
総括
1. 目的
- (1) 当センター研修生と日本の中学、高校の教員、生徒との交流の機会を準備する。
- (2) 交流を通し研修生と日本側教師、生徒の双方に、互いの言語、文化についての理解を深める。
- (3) センターの近隣社会における認知度を高める。
- (4) 交流成果を学会発表、論文投稿などで公開する。
- (5) 研修生の帰国後、交流成果をどう活用しているかにつき、情報収集の方法をより具体化・精緻化し、フォローアップ調査を充実させる。(2005年度の目標)
2. 果たした役割
- (1) 当センターにおいて、研修と日本の中学、高校との交流を開始した
- (2) 交流を繰り返し実施することで、交流の型を開発し、定型化した。
・情報提供収集型
・素材収集型
・授業参観、参加型 - (3) 日本側の交流相手を開拓した。
- (4) 上記目的の(1)~(4)を実施した。
3. 本プロジェクト関係者の企画参加した交流の歴史
横スクロールできます
| 研修名 | 実施日 | 相手校(団体) | 企画実行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 8月19日 | 浦和インターアクトクラブ | 阿部、押尾、中村、前田 |
横スクロールできます
| 研修名 | 実施日 | 相手校(団体) | 企画実行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 短期春 | 6月18日 | さいたま市立浦和南高校 | 高、三原、雄谷、来嶋、篠崎 | プロジェクト外 |
| 2 | タイ | 5月7日 | 越谷総合技術高校 | 北村、根津、八田、前田 | |
| 3 | 短期夏 | 7月30日 | 尾道北高校 | 向井、王、木田、内藤、前田、木谷、北村 | |
| 4 | 韓国 | 8月19日 | 浦和インターアクトクラブ | 押尾、白井、根津、三原、中村 | |
| 5 | 米加英 | 7月22日 | 蕨高校、常盤中学 | 古川、小玉、根津 | |
| 6 | 大洋州 | 1月20日 | 蕨高校(訪問) | 向井、北村 | 希望者のみ |
| 1月17日 | 常盤中学、蕨高校、浦和南高校(リソース収集) | 向井、北村 | |||
| 7 | 長期研修 | 1月21日 | 所沢西高校、和光国際高校 | 根津、八田 | |
| 8 | 中国中等 | 2月17日 | 深谷第一高校 | 王、木谷、島田、前田 |
横スクロールできます
| 研修名 | 実施日 | 相手校(団体) | 企画実行者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイ | 5月12日 | 北本高校 | 北村、長坂、根津、前田 |
| 2 | 短期春 | 6月9日 | 和光国際高校 | 坪山 |
| 3 | 上級研修 | 7月1日 | 熊谷市立女子高校 | 阿部、八田 |
| 4 | 米加英 | 7月10日 | 浦和南高校、常盤中学 | 根津、前田 |
| 5 | 短期夏 | 7月30日 | 尾道北高校 | 押尾、木谷、北村、篠崎、内藤、根津、八田、前田、向井 |
| 6 | 韓国 | 8月17日 | インターアクト・クラブ | 来嶋、白井、長坂、前田 |
| 7 | 中国中等 | 2月15日 | 南稜高校 | 阿部、木谷、柴原、坪山、前田 |
横スクロールできます
| 研修名 | 実施日 | 相手校(団体) | 企画実行者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイ | 5月11日 | 北本高校 | 北村、前田 | |
| 2 | 短期夏 | 7月28日 | 尾道北高校 | 坪山 | |
| 3 | 韓国 | 8月9日 | インターアクト・クラブ | 島田、白井、長坂、前田 | |
| 4 | 中国中等 | 2月25日 | 南稜高校 | 長坂、前田 |
*2005年度は研修担当者のみ交流に参加したため「参加者」とした。
4. 学会発表他
横スクロールできます
| 題名 | 学会・研究会 | 年月日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国人日本語教師と中学校・高校との交流活動の意義と可能性 | 平成15年度第30回全国海外子女教育・国際理解教育研究協議大会 | 2003年 8月5日 |
八田直美、 木谷直之 |
| 2 | 外国人日本語教師と国内中高生との交流−日本語国際センターの訪日教師研修から考える− | 第9回海外日本語教育研究会 | 2004年 1月24日 |
日本語国際センター事業 |
| 3 | 外国人日本語教師への支援活動を通して起きた中高生の意識変化 | 異文化間教育学会 | 2005年 5月28日 |
木谷直之、 前田綱紀 |
| 4 | 教授法科目における文化の扱い−韓国研修でのとり組み− (中高生日本語学習者に伝える日本文化とは−韓国、中国、インドネシアの事例と日本語国際センターの取り組み−) |
第11回海外日本語教育研究会 | 2006年 3月4日 |
日本語国際センター事業 |
日本語国際センター紀要報告
横スクロールできます
| 題名 | 年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 異文化理解を目的とした交流活動のあり方−外国人日本語教師と中高生の協働によって作られる授業− | 2004年 3月発行 |
押尾、木谷、根津、八田、前田 |
| 2 | 外国人日本語教師と高校生ボランティアの協働活動−「素材収集型」交流活動がもたらしたもの− | 2006年 3月発行 |
木谷、前田 |
5. 本年度の実績
- (1) 第11回海外日本語教育研究会でセンターでの取組みの一事例として報告 「中高生日本語学習者に伝える日本文化とは−韓国、中国、インドネシアの事例と日本語国際センターの取り組み−」
日時:2006年3月4日(土)14:00~17:20
会場:国際交流基金 日本語国際センター2階 佐藤ホール - (2) 「2005年度大韓民国高等学校日本語教師研修」の研修修了者を追跡調査4名インタビュー 今年度の目標の一つに、「研修生の帰国後、交流成果をどう活用しているかにつき、情報収集の方法をより具体化・精緻化し、フォローアップ調査を充実させる」というものがあった。この調査の端緒とすべく、訪韓しインタビューした(2006年4月26日~4月28日)。その概要は次のとおり。
[1]目的
1. 文化を通して日本紹介(視覚が重要)
2. ビデオ視聴は日本の間接体験であり日本訪問の予備体験ともなる
3. 動画は日本人の生活実態を簡単に理解させられる
4. 言葉で説明しにくいものを紹介する(例:着物)
[2]素材:ビデオ、写真、実物、キャラクタ人形(展示に利用)
[3]文化要素の利用法:
1. 日韓の差異に気づかせる
2. 質問用紙を準備しておき答えさせる
3. キーワードを提示して作文させる
4. 調べて発表させる
[4]文化要素への生徒の反応
1. 文化紹介は喜ぶ、興味を持つ(浴衣、下駄など)
2. 自分で調査して発表することも反応がいい
[5]研修成果:
文化の直接体験により自信を持った
日本事情で新しい情報を知りおもしろかった
[6]現在利用している情報源
1. みんなの教材サイト
2. 映画のダウンロード(必要な短い部分を使う)