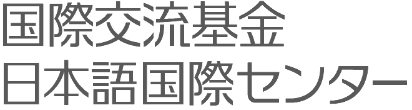第10回海外日本語教育研究会 報告 第2部 タイ国中等教育用日本語教科書『日本語 あきこと友だち』作成 その2
プラパー・セーントーンスック
前田綱紀
2.教科書作成の諸相
1)作成体制
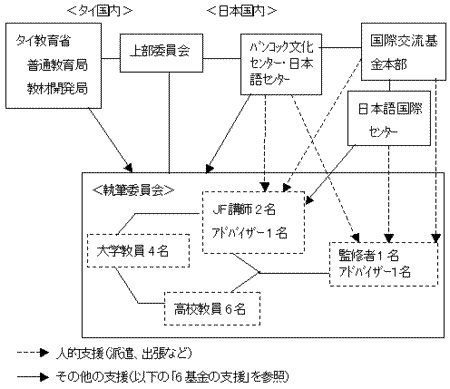
2)作成環境整備
3)教科書作成に必要な資質
- (1) 高校教科書作成に意義を感じ、情熱と使命感を持っている
- (2) 教科書の完成形をイメージとして持っている
- (3) 日本語教科書を作成した経験がある
- (4) 書籍作成のため、数年にわたる共同作業をした経験がある
- (5) 語学のスタジオ録音をした経験がある
4)役割分担
- (1) 監修者:年2度の出張により指導
・教科書作成の現在の潮流とタイでのあるべき教科書の提示
・作成原稿に対する意見、作成体制全般に関する意見提示 - (2) 助言者:年2度の出張により指導
・教科書内容の方向性、構成、内容に関し意見提示と執筆参画 - (3) 執筆委員長:執筆委員会を統括し教科書本冊執筆の中核となる
- (4) 大学教員:本冊執筆の中心
- (5) 高校教員:本冊の内容が学習者に合うかどうか確認、教室活動のアイデアを提供
練習問題、教師用指導書執筆
5)作業速度
編集会議:3年間で合計120回センターで金曜日に開催
合宿会議:1年に2回(4月、10月)
この会議に合わせ監修者とアドバイザーが出張
会議1回で1分冊完成
6)基金の支援内容
Ⅰ 基金(JF本部)・日本語国際センター(NC)の支援内容
- (1) 支援方針の決定、教科書作成調査出張の実施(基金旧日本語課、現派遣・助成課)
- (2) 専門家(主任講師、教科書担当講師)の派遣(基金旧日本語課、現派遣・助成課)
- (3) 監修者・アドバイザーの短期派遣、資料収集、掲載資料の著作権処理など (日本語国際センター制作事業課)
- (4) 教科書素材集『教科書を作ろう』の制作・提供(日本語国際センター制作事業課)
- (5) 高校教員の執筆委員の訪日研修受け入れ(日本語国際センター研修事業課)
Ⅱ バンコク日本文化センター日本語部(旧バンコック日本語センター)の支援内容
- (1) 関係諸方面との連絡調整
- (2) 執筆委員人選の調整
- (3) 担当講師の配置
- (4) 制作支援
- (5) 執筆委員へのコンピュータ貸与
7)執筆委員会体制の背景にある思想
大学教員と高校教員の交流促進
タイの高校教師の養成は大学で行なわれるべき
そのため大学教師が高校教師に接し、実態を知り、指導する機会を提供することを目指す 高校教科書作成は、その構想の中心事業