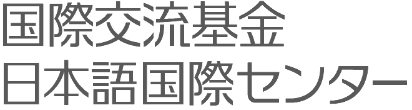第22回海外日本語教育研究会
「日本語国際センターのこれまで・今・これから-日本語教育で人と社会をつなぐ-」
国際交流基金日本語国際センター(以下、NC)は、2019年10月5日(土曜日)に第22回海外日本語教育研究会を開催し、1989年のNC開所以来、取り組んできた現職者教師研修の知見や、昨今の社会情勢を受けた新たな社会的取り組みについて報告しました。140名ほどの方に来場いただき、盛会となりました。
プログラム【PDF:1,344KB】は、全体会と分科会の2部構成で行いました。以下、本研究会の各発表・展示の概要をご報告します。なお、配布された資料や関連資料等もダウンロードできますので、併せてご参照ください。
当日の概要および資料
【全体会】「日本語教師研修のこれまで・これから」(来嶋洋美・八田直美・長坂水晶)
NCで実施してきた、主にノンネイティブ日本語教師を対象とした研修の内容・方法をふり返った上で、今後、時代に合った教師研修を展開していくために何が必要なのか検討しました。その基礎資料として、欧州で開発された外国語教師の資質能力の枠組み等を概観し、日本語教師研修への適用可能性を探りました。アンケートでは「教育者に求められる資質・レベルが常に見直されていることを知り、参考になった」「ヨーロッパ言語共通参照枠(以下、CEFR)だけでなく、欧州で開発されている様々な枠組みを比較しながら見ることが大切だと思った」といった声が寄せられました。


配布資料:
当日提示PPT:全体会「日本語教師研修のこれまで・これから」【PDF:2,208KB】
当日配布資料:全体会資料【PDF:681KB】
【分科会】
「展示/ポスター発表」、「口頭発表」、「カフェ・展示・体験コーナー」の3つを並行して開催しました。それぞれの分科会では、来場者と発表者の間で活発な意見交換が行われました。
展示/ポスター発表
- 教師研修における文法科目
- NCの教師研修における文法科目では、単に「文法」「文型」を教えるのではなく、教師として必要な「文法に対する分析的な視点」の養成を行っています。今回の研究会では次の2つの実践例を報告しました。
「分析的視点や自律性を重視した文法授業(中・上級)の実践」(木田真理・山本実佳)
会場では、授業で使ったハンドアウトや研修参加者が課題にそって作成した成果物などを展示し、それらに関する具体的な質問が多く寄せられました。関連資料:「長期研修Bコースにおける文法授業のシラバス作成—JFSとの関連性からの再考—」(2016年度上半期 調査研究プロジェクト報告書)
「日本語をことばとしてとらえる授業—世界言語の一つとして—」(生田守)
今回の研究会では、授業の概要やシラバス、作成した教材などを展示しました。
「『言語=道具』なの?」、「コミュニケーションに言語は必要か?」、「文法って本当にあるのだろうか?」というようなテーマで来場者の方と有意義かつ楽しいやりとりをしました。関連資料:生田守(2019)「海外日本語教師向け『文法』授業の構築」『マテシス・ウニウェルサリス』20(2), 197-211.
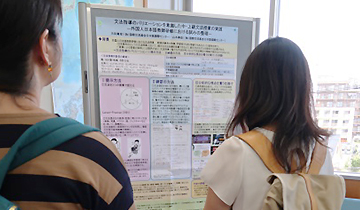

- 「これからの日本語教育を担う若手ノンネイティブ教師のための研修」(押尾和美・石山友之・池田香菜子・大舩ちさと・長坂水晶)
-
NCでは、教授経験の浅い若手教師を対象として、教師としての専門能力、コミュニケーション能力、自己研鑽の能力を高めるために6か月の研修を行っています。今回の研究会では、研修の目標、教授法科目および日本語科目のシラバスや成果物、ポートフォリオなどを展示し、報告しました。来場者からは日本語シラバスについての質問や、ポートフォリオを取り入れた評価について質問が多く寄せられました。

- 「JF生活日本語Can-doを学習目標とした教材の開発」(Can-do開発:菊岡由夏・高偉建・伊藤由希子/教材開発:磯村一弘・藤長かおる・伊藤由希子・湯本かほり・岩本雅子・羽吹幸)
-
NCでは、外国人が日本で出合う生活場面において必要となる「JF生活日本語Can-do」を開発し、それを学習目標にした新たな日本語教材を制作しています。今回の研究会では、8月末に公開した「JF生活日本語Can-do」の概要と開発過程、および、新教材のシラバス案と教材サンプルを紹介しました。会場では、公開中の資料を実際に見ながら、活発な意見交換が行われました。「JF生活日本語Can-do」や開発中の教材の概要について、多くの方に知っていただく良い機会になりました。

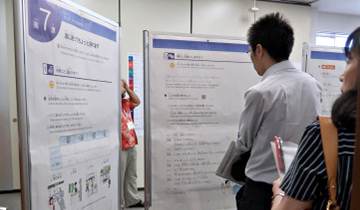
- 「海外におけるビジネス日本語教育のための教師研修」(根津誠・木谷直之)
-
NCでは、海外で教える教師を対象としたビジネス日本語教育のための約5週間の研修を今年度新たに実施します。今回の研究会では、海外のビジネス日本語教育の実態調査の結果と、それを基にした研修デザインを紹介しました。会場では、ビジネス日本語学習の多様性や最近の状況について、来場者の方それぞれの立場をふまえた意見交換がありました。
口頭発表
- 「JF日本語教育スタンダードのCan-doの妥当性の検証」(柴原智代・夷石寿賀子)
-
CEFRを参考にして開発されたJF日本語教育スタンダード(以下、JFS)は、日本語の特徴から見たときCEFRのレベル感が同様に適用できるのかが議論されてきました。NCでは、2018年度にCEFRの検証方法を参考にJFSのCan-doの妥当性を検証しました。検証結果は現在分析中のため、今回の研究会では、JFSの意義、検証の背景や手法について報告しました。研究会当日は、報告を聞くだけでなく、検証プロジェクトの過程で作成されたJFS学習者のレベル別サンプルを聞いて、学習者のパフォーマンスを評価したり、実際の検証と同じく自分の学習者をイメージしてCan-doで評価するという体験もしてもらいました。報告書の公開は年度内を予定しています。

※報告書を「JF日本語教育スタンダードサイト」で公開いたしました。
カフェ・展示・体験コーナー
来場者が語り合う場として、カフェを用意しました。展示を見に行く合間に、カフェでくつろいだり、「日本語教育で人と社会をつなぐ」という今回のテーマについて、コメントを書いたりしていただきました。来場者の方と現在、NCで開催されている研修の参加者がお互いの日本語教育機関について語り合う姿も多く見られました。

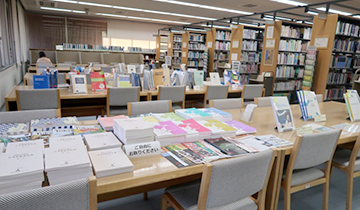
国際交流基金日本語国際センター
教師研修チーム
電話:048-834-1181 ファックス:048-834-1170