平成12年度 国際交流基金賞/奨励賞
国際交流基金では、昭和43年(1973年)以来、毎年、学術、芸術、その他の文化活動を通じて、日本に対する海外の理解、或いは日本人の対外理解を深め、国際相互理解・国際友好親善を促進することで、国際文化交流に特に顕著な貢献があり、引き続き影響力が大きいと認められる個人・団体に「国際交流基金賞」を、顕著な業績をあげられ、今後ますます活躍が期待される個人・団体に「国際交流奨励賞」を授賞し、国際交流活動の顕彰を行なっています。この度本年度の受賞者が決定しましたので、お知らせいたします。
こちらで授賞式当日の模様と各受賞者のスピーチ全文がご覧いただけます

国際交流基金賞

- 池 明観
翰林大学校翰林科学院教授、日本学研究所所長
歴史と文化に関する分野で永年にわたって日韓関係の改善に尽くし、韓国で最大規模の日本学研究所を創設するなど、近年の日韓関係の好転をもたらすうえで計り知れない貢献を行なった。
経歴
| 1954 |
ソウル大学校宗教学科卒業 |
|---|---|
| 1958 | ソウル大学校宗教学科修士課程修了 |
| 1960 | 徳成女子大学助教授 |
| 1964 | 月刊誌「思想界」主幹 |
| 1966~1972 | 徳成女子大学教授 |
| 1972~1986 | 東京女子大学客員教授 |
| 1986~1993 | 東京女子大学教授 |
| 1994~現在 | 翰林大学校翰林科学院教授、同院日本学研究所所長 |
| 1997~1999 | 日韓歴史研究促進に関する共同委員会 韓国側座長 |
| 1998~現在 | 日韓文化交流政策諮問委員会委員長 |
| 1999~現在 | 日韓文化交流会議 韓国側座長 |
| 2000~現在 | 韓国放送公社(KBS)理事長 |
著作等
「日韓関係史研究-1965年体制から2002年体制へ」(1999年、新教出版社)
「ものがたり朝鮮の歴史」(1998、明石書店)
「韓国-民主化への道」(1995、岩波書店)
「人間的資産とはなにか」(1994、岩波書店)
「チョゴリと鎧」(1988年、太郎次郎社)
「破局の時代にいきる信仰」(1985年、新教出版社)
「日韓文化史」(1980年、高麗書林)他多数
国際交流基金賞

- 石井 米雄
神田外語大学学長
永年にわたり、歴史・宗教・言語など様々な分野にわたり研究者として国際的に多大な研究業績を上げ学術の振興に貢献するとともに、日本のアジア研究の国際化とアジア理解の促進など国際交流に多大な貢献をしてきた。
経歴
| 1955 | 東京外国語大学(タイ語専攻)中退、外務省入省 以後、10年間にわたりアジア局、内閣大臣官房、在タイ日本国大使館等に勤務ソウル大学校宗教学科卒業 |
|---|---|
| 1965 | 京都大学助教授 |
| 1967 | 京都大学教授 |
| 1980 | 京都大学東南アジア研究センター所長 |
| 1990 | 京都大学名誉教授、上智大学教授 |
| 1991 | ユネスコ・東アジア文化研究センター所長 |
| 1992 | 日本学術振興会学術顧問 |
| 1993~1994 | 上智大学アジア文化研究所所長 |
| 1995 | 神田外語大学学長 |
| 2000 | 上智大学アジア文化研究所名誉所員 |
受賞歴等
| 1987 | タイ王国白象3等勲章 |
|---|---|
| 1995 | 紫綬褒章 |
著作等
「上座部仏教の政治社会学-国教の構造」(1975、創文社)
「東南アジアからのジャンク・トレード」(1998、シンガポール東南アジア研究所、原題「Junk Trade from Southeast Asia」として英文で出版)
「タイ近代史研究序説」(1999、岩波書店)
国際交流奨励賞
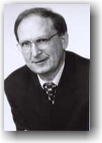
- ウィリー・F・ヴァンドゥワラ
ルーヴァン・カトリック大学文学部東方・スラブ学科長、日本学専攻課程教授
ベルギーにおける日本研究の先駆者として、研究及び後進の育成に尽力。ルーヴァン・カトリック大学を欧州有数の日本学研究機関として確立するとともに、日本の研究機関との学術交流にも積極的に取り組むなど、日本とベルギー、更には欧州を結ぶ国際的な日本研究者として一層の活躍が期待される。
経歴
| 1972 | ゲント大学卒 |
|---|---|
| 1972~1975 | 大阪外国語大学及び京都大学に留学 |
| 1976 | ゲント大学にて博士号取得 |
| 1977 | 京都大学人文科学研究所共同研究員 |
| 1978~1981 | ルーヴァン・カトリック大学講師 |
| 1985 | ルーヴァン・カトリック大学日本研究講座を創設 |
| 1981~1989 | ルーヴァン・カトリック大学東方研究学部日本研究主任助教授 |
| 1989~ | ルーヴァン・カトリック大学東方研究学部日本研究教授 |
| 1993 | 国際日本文化研究センター客員教授 |
著作等
「Basho, dichter zonder dak, Haiku en poetische reisverhalen(芭蕉、屋根のない詩人:俳句と詩的旅行記)」(1985、Peeters)
「Japan-Het onvoltooide experiment(日本という未完の実験)」(共著、1989、 Drukkerij-Uitgeverij Lannoo)
「富岡鉄斎」(共著、1989、国際ユーロパリア財団)
「Schertsend geschetst. Haiku-schilderingen van de 17de tot de 20ste eeuw uit de verzameling Kakimori Bunko(柿衞文庫収蔵の17世紀から20世紀の俳画」(共著、1989、国際ユーロパリア財団)
「Tawara Machi. De dag van het slaatje」(「サラダ記念日」オランダ語訳、共訳、1989、Drukkerij-Uitgeverij Lanoo)
関連サイト
ルーヴァン・カトリック大学日本研究講座 http://japanology.arts.kuleuven.ac.be/
国際交流奨励賞
- ハイファ博物館ティコティン日本美術館


中近東最大の日本美術館として、40年間にわたり日本文化の紹介、日本とイスラエル及び中近東地域の相互理解促進に取り組んできた。
沿革・概要及びこれまでの主要事業
中近東地域最大規模を誇る7,000件余の日本美術・工芸品を収蔵。日本文化の様々な側面を紹介する企画展を毎年数回にわたり開催しているほか、日本文化紹介の講座・ワークショップなども実施している。
| 1956 | ユダヤ系オランダ人建築家で美術収集家のフェリックス・ティコティン氏の遺志により日本美術コレクションがハイファ市に寄贈される |
|---|---|
| 1959 | ハイファ市議会により日本美術館の建築が決定される |
| 1960 | ティコティン日本美術館開館。開館記念「ティコティン氏収蔵美術品」展 |
| 1961 | 「墨絵風景画」展、「歌川国芳」展 |
| 1965 | 「現代日本版画」展、「現代日本写真」展 |
| 1967 | 「日本美術にみるユーモア」展 |
| 1969 | 「日本美術における西洋」展 |
| 1972 | 「20世紀初期の木版画」展 |
| 1975 | 「日本の風景画」展 |
| 1980 | 「現代日本版画」展 |
| 1982 | 「美人画:日本美術における女性」展 |
| 1983 | 「歌舞伎画」展 |
| 1987 | 「日本映画ポスター」展(エフッド・アビシャイ・コレクション) |
| 1988 | 「東海道五十三次」展 |
| 1995~96 | 「神の道:日本美術に見る宗教」展、「波:鯉江良ニの陶芸」展 |
| 1998 | 「侍」展(鎧・刀剣・浮世絵の展示)、「インク・マークス」石井和夫書道展 |
| 1999 | 「ブラック・ゴールド」日本漆器展 |
| 2000 | 「ファンタスティックス」(ティコティン・コレクション収蔵扇画)展 |
国際交流奨励賞
- 大同生命国際文化基金


翻訳出版事業等の着実な活動を通じ東南アジアと日本の相互理解の促進に寄与し、また世界各地域に関する学術的研究の奨励に多大な貢献をしてきた。
沿革及び目的
大同生命保険相互会社の創業80周年を記念して、1985年に設立され、わが国と諸外国との文化交流の実施・助成を通じて、国際相互理解の推進を図り、わが国の国際化に貢献することを目的としている。
活動内容
- 1.大同生命地域研究賞の贈呈:世界各地域に関する学術的研究を奨励するための顕彰事業。
- 2.翻訳出版事業
- (1)アジア諸国の現代文芸作品の日本語翻訳出版(「アジアの現代文芸シリーズ」):アジア諸国の現代文芸作品のうち、わが国への紹介が望まれるものを選考のうえ、翻訳・出版。アジアの国々の今日の姿をそれぞれの国が生んだ文芸作品を通じて理解せんとすることを目的としている。既刊の9カ国34作品は全国の大学、公立図書館などに寄贈。
- (2)アジア諸国への翻訳出版(「ジャパニーズ・ミラーズ」シリーズなど):アジア諸国において、わが国への一層の理解を深める目的で、日本図書ジア諸国語への翻訳出版を実施。3カ国語6作品を既に刊行している。
- 3.大同生命国際文化基金:オックスフォード大学出版会(OUP)と提携し、わが国研究者の優れた業績を英文出版助成する。
- 4.大同生命国際文化基金外国人奨学金制度:本財団が指定する大学及び研究機関に在学する外国人に奨学金を支給し、国際相互理解に寄与する人材の育成をはかる。
- 5.日本文献の寄贈:日本語教育の推進、国際相互理解の促進の為、日本語学科のあるタイの3大学に日本語図書文献を寄贈。
- 6.協力・助成事業:各種国際文化交流事業への支援。
