日本語教育通信 日本語の教え方 イロハ 第9回
日本語の教え方
このコーナーでは、基本的な教授理論、教授知識を解説します。
日本語教授法に関する基礎固め、知識の再点検にお役立てください。
【第9回】日本事情や日本文化の教え方 —日本語の授業の中で—
日本語国際センター専任講師 簗島史恵
日本事情や日本文化の扱い方
外国語教育の中で「文化を教える」目的や方法は、現在、いろいろな国で考えられています。それによると、今までの「文化に関する授業や活動」が、主に「伝統文化」を取り上げることが多かったのに対し、これからは、それだけではなく、現代の「日常生活」や「日常的な言語行動」も取り上げたほうがいい、という考え方が目立ちます。もちろん、日本語を勉強している人たちの中には、「自分の国とは違うめずらしいもの」に興味を持っている人も多いでしょう。けれども、特に若い学習者にとっては、日本の同じ時代の日常的な生活の方が、自分の毎日の生活や自分の身近な人たちと比べることができます。
今回紹介する活動例は、そのような考え方の一つ、米国の“Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century” で提案されている文化理解の方法を取り入れたものです。この中では、文化を次の図1のように整理して考え、文化理解のための方法を提案しています。
図1 3つのP
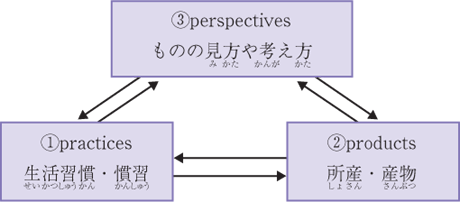
(『国際交流基金日本語教授法シリーズ11 日本事情・日本文化を教える』ひつじ書房より)
私達の目に見えるのは、①と②の部分ですが、それは、本当は、背後にある③と密接に関係しています。ですから、授業の中でも、いろいろな素材を使って、まず、学習者に①や②をしっかり観察させたり、実際に体験させたりして、さらに、③について、考える機会を作ることが必要です。
授業の中での活動のプロセス
例えば、次の2枚の写真を見てください。これは、日本の高校のお昼ご飯の様子です。
まず、この写真から、「生活習慣や慣習」(①)と思われるものと、「文化的所産・産物」(②)と思われるものを探してみます。写真の中の人はどんな様子か、どんな行動をしているか、写真に写っているものは何か、どんなものかを、観察します。まず、一人ずつ、じっくり素材を見てから、自分が発見したものをペアやグループ、クラスで友だちと共有します。


1枚目:「みんなの教材サイト」
2枚目:「であい」 より
| 自分たちとの共通点 | 自分たちとの相違点 | |
|---|---|---|
| ①習慣・慣習 |
|
|
| ②所産・産物 | 机 椅子 黒板 ペットボトル パン お弁当を包む布 |
ごはん はし はし箱 ペットボトルのカバー 黒板の落書き |
観察では、自分達と「異なる点」だけでなく、「共通点」も出すほうがいいでしょう。そうすると、その写真に写っている日本人達に親近感を持つことができます。そして、違う国の人にも共通点があることに気づいたり、逆に、隣の友だちと違うところがあることを知ったりすることができます。つまり、このような観察が、いつも、自分の国と日本を比べるだけにならず、「多様なものを見る目、知る目」を養うことにつなげられ、より広い視野で文化を理解しようという気持ちを持てるようになります。
次に、このように観察したものから、どのような背景や価値観などが考えられるか、自由に言ってみましょう。同じ行動を見ても、「好きだ」とか「私もやってみたい」と思う人もいるし、「どうしてそんなことをするんだろう」「変だ」と思う人もいるでしょう。できれば、まわりの人たちとお互いの意見を伝えたり、ディスカッションをしたりしてみましょう。もちろん、母語を使ってもかまいません。
活動に多くの時間を使うことができる場合は、日本語の授業の要素も取り入れて、いろいろなタスクとして行うこともできます。(具体的な活動例に関心がある方は、『国際交流基金 教授法教材シリーズ11 日本事情・日本文化を教える』をご覧ください。)
活動に使う素材
ここまで述べてきたような活動は、特別な時間を作らなくても、することができます。日本語の教科書に出ている「文化に関するコラムや紹介文」のトピックに合わせてもいいし、教科書の「本文」の中のことばや場面、また、授業の練習で使ったことばを扱ってもいいです。活動に使える時間によって、やり方も調整して行うことができます。
活動で使える素材は、写真だけでなく、日本語の授業に用いる映像(動画)、レアリア、データなど、いろいろあります。海外でも、教材やインターネットなど、入手できるものを使って行うことができます。
| 文型や トピック |
利用できる素材 | 観察できること(例) |
|---|---|---|
| 時間 | 営業(診療、開館)時間が書かれている看板の写真 | いろいろな機関の営業時間 看板の色、書き方 |
| ~が あります |
部屋の写真やビデオ | 家の間取り、部屋の大きさや様子 |
| コンビニの写真やビデオ | 品物の種類や並べ方 店員さんの態度や行動 お客さんの行動 |
|
| 買い物 | ||
| スーパーのチラシ | 値段(物価)、売り方 品物の人気 |
|
| お菓子の袋やパッケージ | 色や文字の使い方 品物に対する価値観 |
素材は、できるだけ複数のもの、多様なものを用意することが望ましいでしょう。例えば、初級の授業で「朝ごはん」という言葉が出てきたとき、左のような写真だけ見せると、日本人がみんな、このような部屋でこのような朝ごはんをこのように食べていると思ってしまいがちです。右のような違う環境や違う形の朝ごはんの写真を見せることで、日本にも多様な「朝ごはん」のスタイルがあることに気づき、自分たちの国にも同様にいろいろなバリエーションがあることに気づけるでしょう。
|
|
|
|
| 「みんなの教材サイト」より | ||
活動の意義
このような活動の目的は、学習者の「目」と「頭」を育てることで、日本人の考え方や価値観について最終的に結論を出すことではありません。学習者は、このような経験を積み重ねることによって、自分とは違うもの、新しいものに接したとき、ただ「なんとなくいやだ」とか「あまり好きになれない」と考えずに、自分との共通点を見出したり、違う理由を考えたりすることができるようになります。特に、学習者一人ではなく、グループやクラスの友だちと意見を交換すると、文化の多様性や個別性に対する「気づき」を促す上でとても効果的です。この力は、日本語という外国語を勉強することによって身につけることができる、一生の力になるでしょう。
参考文献
- National Standards foreign Language Education Project(1999)
"Standards for Japanese Language Learning". Standard for Foreign Language Learning in the 21st Century. - 国際交流基金(2010)『国際交流基金日本語教授法シリーズ11 日本事情・日本文化を教える』ひつじ書房
- 「みんなの教材サイト」 http://minnanokyozai.jp/
- 国際文化フォーラム「であい」 http://www.tjf.or.jp/deai/index.html


