国境を越えた創造の現場から
2025年度 舞台芸術国際共同制作 オブザーバー
- 採用案件一覧
- オブザーバー
- オブザーバー制度とは?
- さまざまなバックグラウンドを持つ第三者が、オブザーバーとして舞台芸術の制作過程を記録し、報告書やイベントを通して公表する制度です。プロセスを共有することで、舞台公演の国際共同制作の過程を一般に広く伝えていき、より多くの公演団やアーティストによる海外とのコラボレーションに役立てます。また、普段接することのできない国際的な現場の様子から、新たな形での国際交流への気付きを提供することを目指します。
オブザーバー

田中里奈(たなか りな)
担当作品:温又柔×Jang-Chi×ネス・ロケ(フィリピン)×李銘宸(台湾)『クルージング:旅する舌たち』
興行研究者、批評家。京都産業大学文化学部准教授。一般社団法人ハラスメント対策協会・ハラスメント対策アドバイザー。神奈川大学在学中より企業博覧会での通訳、ODU Japan㈱セールス・サポートを経て、2017年度オーストリア国立音楽大学音楽社会学研究所招聘研究員。2020年明治大学大学院にて博士(国際日本学)取得。2019年International Federation for Theatre ResearchよりHelsinki Prize受賞。近年の分担執筆・寄稿に『Milestones in Musical Theatre』(Routledge, 2023)、『The Routledge Companion to Musical Theatre』(Routledge, 2022)、雑誌『Sound Stage Screen』『メルキュール・デザール』など。

砂金有美(いさご ゆみ)
担当作品:小㞍健太×ハネス・マイヤー(ドイツ)『Engawa, The Self in Season』
編集者。早稲田大学文学部演劇映像コース演劇系卒。在学中、間瀬幸江に師事。株式会社筑摩書房第一編集室に現在所属し、文芸および人文系ジャンルを中心に単行本、文庫、web連載等担当。2014年、作家・恩田陸のバレエダンサー&コレオグラファー小説『spring』シリーズ企画立ち上げ。2024年、本編刊行。
津田啓仁(つだ ひろと)・船橋陽馬(ふなばし ようま)・白田佐輔(はくた さすけ)
担当作品:みんなのしるし×Omah Gamelan(インドネシア)×陳 光輝、陳 世興(台湾)『髪長姫 The Thread of Heaven: The Legend of Kaminaga-hime』
秋田県を拠点に活動する文化人類学者でアーティストの津田啓仁と、写真家でマタギの船橋陽馬、記録と発信に関心をもつコーディネーターの白田佐輔(NPO法人アーツセンターあきた)による即席のコレクティブユニット。調査・記録・表現や、伝統と現代を横断しながら、地域の文化や自然環境、人々の営みを多角的に探究することを試みる。
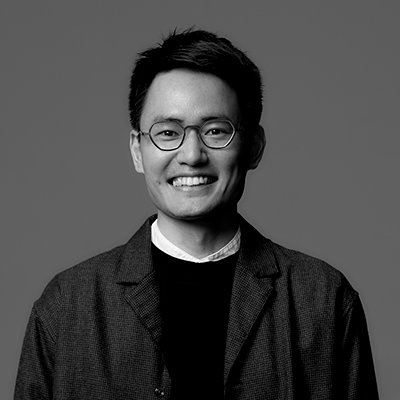
津田啓仁(つだ ひろと)
文化人類学者、アーティスト。東京大学大学院で修士号(文化人類学)を取得後、現在は秋田県を拠点に干拓地・八郎潟を取り巻く自然環境について調査・研究している。並行して、街の朝市や酒造会社、デザイナーの制作活動など幅広い対象を人類学的な方法を用いながら複数人で調査するプロジェクトなどを進行中。学生時代からコンテンポラリーダンスの公演に継続的に出演するなど、身体を用いた表現行為にも関心がある。

船橋陽馬(ふなばし ようま)
写真家。1981年男鹿市(旧若美町)出身。高校卒業後、上京。東京、名古屋、ロンドンの花屋で仕事をし、2009年帰国後、多摩美術大学に入学。在学中よりフォトグラファー・神林環氏に師事。大学卒業後よりフォトグラファーとして雑誌・広告等で活動。 2013年から、マタギ発祥地、そして根子番楽で知られる北秋田市阿仁の根子集落に住み、マタギ文化、山間部の人々の暮らしを記録し続けている。秋田県庁が発行するフリーマガジン『のんびり』、全日空ANA機内誌『翼の王国』、みずほ総合研究所発行『Fole』、青森県庁発行『青森の暮らしぶりを訪ねる旅』などの撮影に携わる。秋田公立美術大学附属高等学院特別講師。 2022年3月、焙煎所「根子マタギコーヒー」をオープン。

撮影:髙田恭輔
白田佐輔(はくた さすけ)
NPO法人アーツセンターあきた コーディネーター。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻卒業。在学時は、学生のフィールドワークや制作の様子を取材、撮影した配信番組を企画。現在はZINEの制作やインタビュー記事を通して、秋田で出会った人々のことを記録・発信している。2023年より秋田市文化創造館勤務。リソグラフ印刷機の活用プログラム「リソの日」や、誰もがその日限りのー日店主となって、語り合うだけの場「カタルバー」などを担当。

稲垣貴俊(いながき たかとし)
担当作品:た組×四把椅子劇團(台湾)『どうも不安な様子』
ライター・編集者。木ノ下歌舞伎 企画員。ハリウッド映画・アジア映画を専門に、評論やコラム、インタビューなどを書籍・雑誌・映画パンフレット・ウェブメディアほか多数の媒体で執筆。国内舞台作品のリサーチ・コンサルティングも務める。近年の参加作品に、東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』(2024)、COCOON PRODUCTION 2022『パンドラの鐘』(2022)など。

友川綾子(ともかわ あやこ)
担当作品:鈴木ユキオ×Stopgap Dance Company(英国)『Beyond(仮)』
京都芸術大学芸術学科卒。アートマーケットから地域に根ざした公的プロジェクトまで幅広い現場を経験。メディアでの編集・執筆、NPOでの広報・ファンドレイジングなどを通じ、アートと社会を多層に「つなぐ」仕事に注力してきた。2019年には米オレゴン州ポートランドにて心理学の集中プログラムを履修し、国際的かつ心理的な視点を培う。2020年、ヨコハマ・パラトリエンナーレ広報ディレクター。2021年にgallery ayatsumugiを設立し、現代アートの展覧会を各地で企画・開催。2022年、ICF国際コーチング連盟ACC認定。アートプロジェクトのコンサルテーションやマネジメントを手がけている。

竹谷多賀子(たけや たかこ)
担当作品:鳥の劇場×トム・ポウ&ガロウェイアグリーメント(英国)『TOWA MURA』
龍谷大学経営学部准教授。同志社大学大学院嘱託講師。博士(経済学)。文化経済学の観点から、地域の持続的発展をめざす文化芸術活動の多様な展開を研究。文化経済学会〈日本〉理事。丹波篠山市日本遺産・創造都市推進委員会委員、ユネスコ創造都市ネットワーク丹波篠山市国際会議実行委員会顧問・アドバイザー。主著に『クリエイティブツーリズム論ツーリストとコミュニティの共創プロセス』(単著2025年)、『創造社会の都市と農村』(分担執筆2019年)、主な論文に「クリエイティブツーリズムによる過疎地域の持続発展—珠洲市におけるアートツーリズムの可能性—」(単著2022年)など。
[お問い合わせ]
国際交流基金(JF)
文化事業部舞台芸術チーム
電話:03-5369-6063
E-mail:pa@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください。)
