海外日本語教育レポート 第14回 カナダ・アルバータ州の初等・中等教育における日本語教育カリキュラム
海外日本語教育レポート
このコーナーでは、海外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。
カナダ・アルバータ州教育省日本語アドバイザー
(国際交流基金派遣専門家)
室屋 春光
カナダ
カナダでは英語とフランス語が公用語であることはよく知られていますが、ケベック州以外の州では主に英語が使われています。それらの英語圏諸州の初等・中等レベルの言語教育ではフランス語は実質的には他の諸言語(外国語)と同列に扱われているためフランス語が圧倒的に優勢で、他の言語は残されたパイを奪い合うような形になっているというのが実情です。また、連邦制国家であるため初等・中等教育の事情は州によって多様で、日本語教育の事情も州によって大きく異なります。
アルバータ
アルバータ州では初等中等教育レベルでフランス語だけではなくいろいろな言語*を教えようとする教育政策がとられています。アルバータ州内の小中高校で教えられている言語は学習者数の少ないものもすべて含めると約20を数え、カナダの他の州と比べると多彩です。学習者数が多く教育省策定のカリキュラムがある言語にはフランス語、スペイン語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ウクライナ語、パンジャビ語などがあります。アルバータ州教育省はこのような多言語教育政策に対応するために、ここ数年初等中等教育のための各言語カリキュラムの策定あるいは改訂の作業を進めています。
- *アルバータ州ではInternational Languagesという言葉が使われていますが、ここでは便宜的に「言語」という言葉に置き換えます。
アルバータの言語教育カリキュラム
現行の、あるいはこの1、2年のうちに刊行予定のアルバータ州の言語カリキュラム(フランス語を除く)は、すべて「The Common Curriculum Framework for International Languages」という各言語共通の言語教育カリキュラムの枠組みを記述したカリキュラムモデル文書に基づいて策定されています。この文書(The Common…)は、アルバータ、サスカチュワン、マニトバのカナダ中西部3州の教育省が合同で進めた「Western Canadian Protocol for Collaboration in Basic Education」という共同作業プロジェクトによって作成され、2001年に刊行されました。
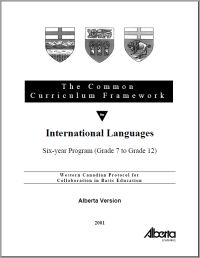
The Common Curriculum Framework for International Languages
- Six-year Program (Grade 7 to Grade 12) Alberta Version
Western Canadian Protocol for Collaboration in Basic Education, 2001
この文書では効果的な言語学習について以下のような考え方を示しています(抜粋)。
この枠組み文書(The Common…)は、「生徒は以下のことができるようになる(Students will be able to:)」として具体的な学習成果項目(学習後にできるようになっていること)を列挙する、いわゆる成果志向型(Outcome-based)のカリキュラムモデルです。

カナダ・アルバータ州エドモントンのHarry Ainlay高校で日本語を教えている
伊藤Fedrau美恵子先生の生徒たちです。巻き寿司を作っています。
全体は「実用(Application)」、「言語能力(Language Competence)」、「地球市民(Global Citizenship)」、「各種方策の援用(Strategies)」という四つの大きな部門に分けられ、それぞれの部門の下にいくつかの学習目標項目があり、さらにそれぞれの学習目標項目の下に具体的な学習成果項目が列挙されています。
どの部門のどういう学習目標の下にどういうことが具体的な成果として挙げられているか、一、二、例を挙げてみましょう。
| 部門 | 実用 |
|---|---|
| 学習目標 | 情報をやりとりする |
| 成果 | 簡単な情報を交換できる(中学1年) |
| 成果 | 経歴、報告などのような特定のトピックについて詳細な情報を交換できる(高校3年) |
| 部門 | 各種方策の援用 |
|---|---|
| 学習目標 | 言語の使用 |
| 成果 | メモを見たりして話を進めるための方策を使うことができる(高校1年) |
| 成果 | 話を継続させるために各種の方策から適切なものを選んで使うことができる(高校3年) |
この枠組み文書は学習を始める学年の違いによって3年プログラム(高1-3)、6年プログラム(中1-高3)、9年プログラム(小4-高3)の三つが用意されていて、アルバータ州教育省のウエブサイトからダウンロードすることができます(PDFファイル)。
Three-year Program (Grade 10 to Grade 12)
Three-year Program (Grade 10 to Grade 12)
Six-year Program (Grade 7 to Grade 12)
Six-year Program (Grade 7 to Grade 12)
Nine-year Program (Grade 4 to Grade 12)
Nine-year Program (Grade 4 to Grade 12)
日本語のカリキュラム - 日本語学習プログラム
アルバータ州の各学習科目のカリキュラム(学習指導要領)は「学習プログラム(Program of Studies)」と呼ばれ、教育省のCurriculum Branchが策定・刊行しています。各言語の学習プログラムはすべて上に述べた枠組み文書に基づいて作成されているので、それぞれの言語の必要に応じて若干の手直しがされてはいますが、どの言語の学習プログラムも基本的には内容にそれほどの違いはありません。日本語の学習プログラムもこの枠組み文書(The Common…)に基づいて作成されています。2006年12月の時点では日本語の学習プログラムは以下のものが刊行されていて、教育省のウエブサイトからダウンロードすることができます(PDFファイル)。
Program of Studies - Japanese Language and Culture Three-year Program 10-3Y, 20-3Y, 30-3Y
高校1年から日本語を学びはじめるコースのための学習プログラム(3年プログラム)
Program of Studies - Japanese Language and Culture Three-year Program 10-3Y, 20-3Y, 30-3Y【PDF:外部サイト】
Program of Studies - Japanese Language and Culture Six-year Program Grades 7-8-9
中学1年から日本語を学び始めるコースのための学習プログラム(6年プログラムの前半)
Program of Studies - Japanese Language and Culture Six-year Program Grades 7-8-9
Program of Studies - Japanese Language and Culture Six-year Program 10-6Y, 20-6Y, 30-6Y
中学から学び始めた生徒が高校で引き続き日本語を学ぶというコースのための学習プログラム(6年プログラムの後半)
Program of Studies - Japanese Language and Culture Six-year Program 10-6Y, 20-6Y, 30-6Y

カナダ・アルバータ州エドモントンのWP Wagner 高校で教えている
坂口宗(さかぐちはじめ)先生の日本語クラスの写真です。
日本語9年プログラムは小学校4年と5年の2年間分がほぼ完成していて、暫定版をダウンロードすることができます。小学校6年の分も2007年秋ごろまでには刊行される予定ですが、中高校の部分は今後2、3年の間に漸次刊行されることになっています。
Program of Studies - Japanese Language and Culture Nine-year Program Grades 4-5
Program of Studies - Japanese Language and Culture Nine-year Program Grades 4-5
学習プログラムに準拠した指導の手引き
学習プログラムそのものは学習成果(Outcome)を組織立てて列挙したものなので、期待されている成果を実現するためには具体的にどのような言語内容を教えればよいかという指標にはなりません。学習プログラムを補完し現場の教師の授業を支援する目的で、教育省のLearning & Teaching Resources Branchでは各言語の学習プログラムに準拠した「指導の手引き(Guide to Implementation)」という文書を作成し配布しています。
この指導の手引きは、「授業計画」、「授業の上手な進め方」、「学習上特別な支援が必要な生徒について」、「評価」、「学年ごとの具体例」、というような章があり、全体では数百ページにも及ぶ大部の文書です。最後の「学年ごとの具体例」の章では、学習プログラムに列挙された成果の一つ一つについて、どのような言語内容を扱いどのような教室活動を行うと効果的かという具体例が示されていて、教師にとってはとても便利で役に立つ教材となっています。
日本語では3年プログラム(高1-3)の「指導の手引き」が2007年度中に発行される予定で、発行と同時に教育省のウエブサイトからダウンロードできるようになります。
日本語3年プログラム用の「指導の手引き」では語彙リストも付録の一部となっています。この語彙リストの作成には、学習プログラム(3年)の内容を吟味して必要と考えられる語彙を抽出するだけでなく、カナダでよく使用されている教科書(「Ima」1・2、「Obentoo」1・2・3、「Adventure in Japanese」1・2、「Kimono」1・2・3)や、ブリティッシュコロンビア州の高校カリキュラムの語彙リスト、オーストラリア・ビクトリア州のVCE語彙リスト、日本語能力試験の語彙リストなども参考にされています。
教育省認定教材リスト
上に述べた「指導の手引き」とあわせて、教育省のLearning & Teaching Resources Branchでは「教育省認定教材リスト(Alberta Authorized Resource List and Annotated Bibliography)」も作成し公開しています。これは初等・中等教育において使用される教材(市販されている教科書や副教材、辞書など)をアルバータ州教育省が規定する基準によって審査し、審査を通過したものは認定リストに加えて教師の参考に資するというものです。教材を審査し認定する目的は、教材そのものがアルバータ州の教師や学習者にとって有用であるかどうかという点を確認することにありますが、あわせて教育的見地から見て好ましくないものを排除するという点も配慮されています。審査認定された教材には簡単な説明や適合する学年・学習レベルも記述されているので教材を選ぶときの参考になります。この「教育省認定教材リスト(日本語用)」は教育省のウエブサイトからダウンロードできます(PDFファイル)。
Japanese Language and Culture Alberta Authorized Resource List and Annotated Bibliography
教育省認定教材リスト(日本語用)
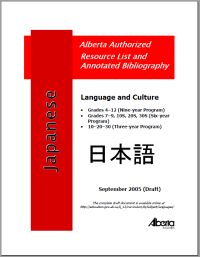
Alberta Authorized Resource List and Annotated Bibliography
Japanese Language and Culture
・Grades 4-12 (Nine-year Program)
・Grades 7-9, 10S, 20S, 30S (Six-year Program)
・10-20-30 (Three-year Program)
Alberta Education, September 2005 (Draft)
