海外日本語教育レポート 第22回 コミュニケーションツールとしての日本語 -発表形式の可能性-
海外日本語教育レポート
このコーナーでは、海外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。
【第22回】
シンガポール教育省 語学センター 日本語学科
シニア・ティーチャー
タン・チンイエン
はじめに:シンガポール教育省語学センターの設立
当センターの前身である外国語センターは貿易、観光、科学技術の分野を担う人材の育成のため1978年に設立され、その後1986年にシンガポール教育省語学センターとなった。当センターでは、シンガポールの中等教育、中学校及び高校の学習者を対象に外国語教育を行っている。小学校卒業試験で上位の成績を修めた優秀な生徒が、教育省語学センターで、選択科目として1つの言語を学ぶことができる。設立当時の日本語、フランス語、ドイツ語に加え、マレー語、インドネシア語とアラビア語の課程も増設された。
日本語学科:現状、カリキュラム
シンガポールにおける日本語教育の特徴の1つは、中等教育で第3言語(注1)として日本語教育を行っていることである。当センターの日本語学科は、2010年現在、教員数21名(うち日本人9名)、学習者は中学1年生から高校2年生までで約1600人。2007年に新しいキャンパスの設立により、日本語学習者の定員が大幅に増加した。そして、最新動向としては、2010年から、ラッフルズ高校の日本語プログラムが教育省語学センターの日本語学科に統合されることになり、高校生の人数も増える見通しである。(注2)
当センターでは、日本語学習の最終到達目標を、日本の大学進学においているため、到達レベルは中学4年生でケンブリッジGCE Oレベル試験 (Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level、日本語能力試験3級程度)、高校1年コースで同H1レベル(Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced H1 Level,日本語能力試験2級程度)で、高校2年コースで同H2レベル(Advanced H2 Level,日本語能力試験1~2級程度)の水準である。(注3)
高校のH2レベルの到達目標は日本語で自由にかつ明確にコミュニケーションができ、日本の社会、文化の理解を目指すことである。そのため、センターのカリキュラムは4技能を身につけさせるだけでなく、日本の文化や事情にも興味を持たせ、理解を促す教室活動、課題を多く取り入れている。
教科書は『新文化初級日本語Ⅰ、Ⅱ』及び『文化中級日本語Ⅰ、Ⅱ』(文化外国語専門学校)。授業では文型・文法の学習以外に、聴解練習、ディスカッション、作文、口頭発表、プロジェクトワークなどを通して運用力の向上を図り、さらに高校のコースでは、コースワーク(小論文)などの指導が行われている。
語学センターの学習環境と授業形態
各教室にコンピューターとプロジェクターが設置され、インターネットの接続もできる。フラッシュカード、絵教材などに加え、パワーポイントやウェブサイトの素材(例えば、天気予報、ファーストフードのウェブサイト、ビデオなど)を使った授業を行っている。
学習者は日本語を選択科目として学習しているため、所属の学校の授業が終わってから、当センターの授業を受けにくる。2009年に、従来の週2回、2時間ずつの授業形態からセンターでの週3時間15分の対面授業と自宅での45分のOnline授業に変わった。学習者は毎週日本語学習の一環として自主的に語学センターのポータルを利用して、自宅で45分の学習をすることになっている。
センターにおける指導、活動の紹介: Show & Tell、グループプロジェクトワーク
本レポートでは、コミュニケーション、その中でも、人に自分の思ったことを伝えるところに焦点を当て、中学2年生のShow & Tellと、中学3年生のグループプロジェクトワークの2つの活動を紹介したいと思う。この2つの活動の最大の意義は、初級の段階で既習の文法、文型を使って、人前で発表することによって、学習者が達成感や日本語を話す自信を得、それがさらなる学習意欲の向上や主体性につながることである。また、この活動を通して、クラスメートや教師との理解を深め、よりよい関係を築いていくことも期待できる。
2年生のShow & Tell
目的:学習者の好きなもの、アイドル、動物についてクラスの前で発表することによって、人の前で日本語を話す、発表する自信をつけること。
指導及びプロセス:2年生の2学期、1週目に「私の好きな動物」または「私の好きなアイドル」について作文を書く課題がある。そして、作文の訂正及び清書を3週目に完成させてから、4週目に1回目のShow & Tellの指導を行う。
| (4週目)1回目の指導 |
Show & Tellのスピーチのスクリプトは訂正した作文を基に作成する。但し、訂正した作文をそのまま読み上げるのではなく、聞く人に話しかけるように書き加えたり、書き直したりする箇所が必要であることを指摘する。例えば、Show & Tellのスピーチの前に、必ず、作文にはない挨拶や自分の名前、スピーチのテーマなどを入れること。
|
| (5週目)2回目の指導 |
準備、練習段階の留意点: スピーチをする時の留意点:
|
| (7週目~10週目)発表 |
|
発表のテーマには好きな動物(猫、犬、亀など)、好きなスポーツ(スポーツ、チーム、選手について)、好きなアイドル(日本のみならず、シンガポール、香港、台湾、そして最近アジアで人気のある韓国の人気歌手、グループ、俳優など。時には、政治家について発表する学習者もいる)などがあった。学習者の興味のあるトピックについての発表なので、1人1人の個性が出ていて、聞く側にとっても非常におもしろい経験である。特に、発表者の意外な一面が覗えた時の驚き、または自分と同じ趣味を持つ人を発見する喜びがこのShow&Tellの予想外の収穫だとも言えよう。
3年生のプロジェクトワーク
目的:日本語を「道具」とし、日本語という「媒体」を通して、学習者が自らの考えやアイデアを伝達、発信すること。単に日本語で発表することだけでなく、グループのメンバーと協力しながら、アイデアを考え、練習、発表のあらゆる段階において、他人とのコミュニケーションスキル、リーダーシップを身につけること。
指導及びプロセス:3年生の1学期の終りにプロジェクトワークの説明とグループ分けを行う。プロジェクトワークの課題は、4、5人のグループで、日常生活の中で困っていること、不便だと思うこと、あればいいと思うものなどを見つけ、その改善法を考えて、グループでそのアイデアを発表することである。グループのアウトライン、スクリプトの添削、練習、リハーサルなどの段階を経て、最終的に3学期の最後の2、3週間に渡って、発表を行う。
| (1学期10週目)説明とグループ分け |
|
| (2学期1週目と3週目)アウトライン |
| (2学期9週目)スクリプトの1回目の提出 |
|
| (3学期1週目)スクリプトの訂正 |
|
| (3学期4週目)スクリプトの最終提出及び発表の準備 |
|
| (3学期6、7週目)リハーサル |
|
| (3学期8、9週目)発表 |
|
3年生におけるプロジェクトワークは、学習者自身が周囲を観察し、改善したい項目を見つけ、その改善法を考え、更にそのアイデアを独自の形で聞く人たちに発信する。観察力、分析力、創造性、独創性、更にグループワークでは欠かせない協調性が必要とされる学習プロセスである。
発表された改善法は学習者の想像による道具の設計や、発明、商品の開発、サービスの紹介など様々で、発表の形式も自由となっている。これまでにスキット(寸劇)、テレビのニュース番組、トークショー、企業のプレゼンテーション、商品のプロモーションなどのおもしろいものがたくさんあった。トイレを掃除するロボット、振動するベッド、ドラえもんのようなポケットなどおもしろい発想のものもあれば、アイデアよりも、発表の形式、演出に思いがけない展開、ユーモアに溢れるおもしろいシーンが出てくるものもある。例えば、携帯用の太陽光充電器のスキットでは、テレビ番組「Who wants to be a millionaire」、ビールのコマーシャルのパロディ、そして、最後にスターウォーズのシーンまで出てくる奇想天外な展開があり、学習者の持っている無限の想像力に驚くばかりであった。ここもまた、学習者のグループ、個人の個性がはっきりと出ていて、教師にとって、普段見られない学習者の側面が見られ、そして、プロジェクトワークをしている間に、グループのメンバーの中のリーダシップを発揮できる生徒を知ることができる貴重な機会にもなっている。
新しい試みと今後の課題
2009年シンガポール教育省語学センターの新しい試みとして、3年生のプロジェクトワークの発表を日本語科の文化祭のプログラムの一つとして、取り入れた。おもしろいアイデアやプレゼンテーション、演技が上手なグループを4グループ選び、文化祭に来た120名ぐらいの1、2、3年生の生徒の前で発表した。

3年生のプロジェクトの発表
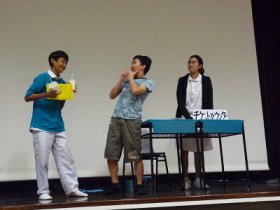
センターの日本文化祭での発表
この新しい試みは発表したグループの生徒にとって、非常によい励みになり、発表を見た生徒にも大変評判がよかった。特に下の学年の生徒には、今、自分が勉強している日本語を、近い将来、プロジェクトワークというおもしろい形で実際に観客の前で披露できると知らせ、日本語の勉強のモチベーションを高めることができた。
ここで紹介したShow & Tellとプロジェクトワークの最大の意義は日本語をコミュニケーションの「道具」として使うことである。ただ試験の成績のためにシラバス、カリキュラム、教科書の文法項目を覚えるという学習行為を越え、学習した日本語を使って、実際に他人に自分のこと、考え、アイデアを伝えることの喜び、達成感こそが、言語学習の最も大きい原動力となるのだ。
しかし、以上の活動を実行するには、時間が必要である。日本語科として直面している最も大きな課題はこれらの活動のために、いかに限られた授業の時間を有効に、効率的に利用するかということである。発表に充てる時間だけではなく、全体の授業時間、聴解練習、会話練習など、全ての教室活動を考慮しながら、進度を調整しなくてはならない。また、3年生のグループプロジェクトの場合は学習者の間の連絡や相談・練習のスケジュール調整に関する指導も必要である。
しかし、コミュニケーションの「道具」としての日本語を目指すために、以上の問題を乗り越える工夫は教師にとって重要な使命なのだろう。
- 注1 シンガポールは多民族国家のためバイリンガル教育政策を取っており、小、中学校では、英語を第1、そして中国語、マレー語、タミール語のうちから1つを第2言語として学習することになっている。
- 注2 今まで、GCEのAレベルの日本語コースはラッフルズ高校と当センターで 履修できたが、2010年に当センターの日本語学科に統合された。
- 注3 ここで達成度、日本語のレベルの目安として日本語能力試験(旧試験)を尺度として使ったが、実はGCEの試験の達成目標、形式及び評価は能力試験と大きく異なり、ここでの比較はあくまでも広く認識されている能力試験における日本語初級、中級のレベルの文法の学習項目の基準である。
Oレベルの試験は、オーラル、文法、読解、聴解、作文と絵作文の項目で構成された4技能を測定し、評価する試験であり、高校のH2では日本語以外、社会、経済、歴史なども学習し、プレゼンテーション、オーラルと筆記試験の他に小論文を書くコースワークもある。 - 注4 Show & Tellの学習者用の評価基準表、Rubrics <添付1【PDF:94KB】>
- 注5 アウトラインの用紙 <添付2【PDF:65KB】>
- 注6 指導は最初の説明の時(1学期の最後の週)から随時行う。指導内容はプロジェクトのテーマ、内容及び発表形式が適切か、グループ内の各メンバーの役割分担が適当かどうかなど。
- 注7 1回目の提出の期限を6月の休みの最初の週にするのは、教師が休み中にスクリプトをチェックしなくてはならないため。チェック済みのスクリプトを3学期の最初の週にグループに返却する。
教師はスクリプトの構成や内容、語彙、表現の適切さ(他のグループの学習者が“聞いて”わかる単語、表現を使うように指導)、正確さなどをチェックする。基本的に全ての文法の間違いを直すのではなくて、学習者自身に訂正させる方針をとっている。 - 注8 プロジェクト発表の評価基準、Rubrics <添付3【PDF:44KB】>
〔参考ウェブサイト〕
シンガポール教育省(Ministry of Education, SINGAPORE)
http://www.moe.sg/
国際交流基金 日本語教育国別情報(シンガポール)
国際交流基金 日本語教育国別情報(シンガポール)
国際交流基金 日本語教育国別情報
国際交流基金 日本語教育国別情報
