ベルリン日独センター 共催シンポジウム 「日独対話から考える食の未来」
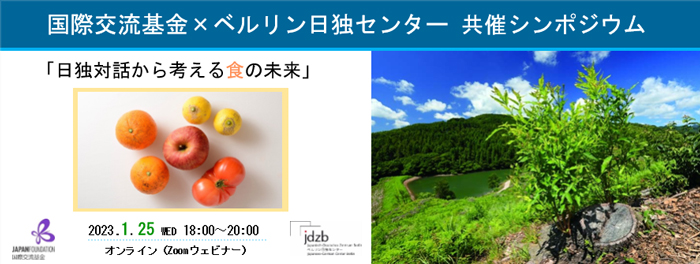
近年、私たちの食を取り巻く環境は大きく変化しています。地球温暖化に伴い自然災害が拡大し、生物多様性が危機に瀕している一方、食のグローバル化が進展し、人口増加に伴い食糧の供給が世界的な課題になっています。食料を安定的に生産・供給して、かつ環境に配慮した持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような食のシステムを考えるべきでしょうか?そこに私たちの社会や地域が持つ食文化は、どのように貢献することができるでしょうか?
本シンポジウムは、ドイツと日本において食と農の分野で活躍する専門家を迎え、両国の食文化や、食のサステナビリティ推進に向けた知見を共有することで、食に関わる日独共通の課題解決に向けた対話の機会とします。
※本シンポジウムは2023年1月25日(水曜日)に実施いたしました。当日の様子はこちらの動画ページからご覧いただけます。
開催概要
| 日時 | 2023年1月25日(水曜日)18時~20時(17時30分開場) ※本シンポジウムは終了しました。 |
|---|---|
| 会場 | オンライン(Zoomウェビナーを使用) |
| 言語 | 日本語、ドイツ語(同時通訳あり) |
| 主催 | 国際交流基金(JF) |
| 共催 | ベルリン日独センター |
プログラム
- 【第1部】基調講演「日本とドイツにおける食の課題」
- 日本とドイツから食の分野に携わる研究者が1名ずつ登壇し、食とサステナビリティ/文化をめぐる両国の現状と課題について講演を行います。
- 登壇者:
- 香坂 玲 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授)
- ヤナ・リュッケルト・ヨーン (フルダ専門大学 教授)
- 【第2部】パネルディスカッション 「食のサステナビリティ推進に向けた日独の取り組み」
- 日独から実務家を中心にパネリストが登壇し、食のサステナビリティ推進のために両国で目指すべき取り組みについて、具体例を交えつつ議論します。
- モデレーター:
- コルネリア・ライアー (べルリン自由大学 教授)
- 登壇者:
- 香坂 玲 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授)
- 林 浩昭 (農林業従事者、国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 会長)
- 松山 麻理 (ブランドエディター/オイシックス・ラ・大地株式会社 らでぃっしゅぼーや通販事業本部 販売企画室)
- ヤナ・リュッケルト・ヨーン (フルダ専門大学 教授)
- マルティーナ・シルナー (フードジャーナリスト)
- ベネディクト・ヘーリン (農業の未来基金 ベルリン支部長)
日本側登壇者プロフィール
【第1部 基調講演/第2部 パネルディスカッション】

香坂 玲(こうさか りょう)
東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授
静岡県生まれ。東京大学農学部卒業。ドイツ・フライブルク大学の環境森林学部で博士号取得。ハンガリーの中東欧地域環境センターに勤務後、 2006年からカナダ・モントリオールの国連環境計画生物多様性条約事務局に勤務。2008~2010年度まで、愛知県名古屋市で開催されたCOP10の支援実行委員会アドバイザーを務め、国連での経験を活かし、手腕を発揮する。
生物多様性条約、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学(IPBES)の政府代表団・専門家として関わる。国連大学高等研究所の客員研究員として里山の評価などにも参画し、WWFジャパン自然保護委員会、ネイチャー・ポジティブ経済研究会のメンバーなども兼務する。
【第2部 パネルディスカッション】

林 浩昭(はやし ひろあき)
農林業従事者、国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 会長
大分県国東市の原木乾しいたけ農家生まれ。東京大学農学部卒業。同農学系研究科博士課程を中退後、1985年に同農学部植物栄養・肥料学研究室助手に採用。1995年から2003年まで同助教授を務める。2004年から国東市の自宅で農林業(原木乾しいたけ、米)を開始し、同時に、くにさき農業協同組合代表理事常務及び大分県立農業大学校長としても活動。

原木乾しいたけ栽培の「ほだ場」
2012年より国東半島宇佐地域における世界農業遺産への申請活動に参加し、2013年の認定後は、国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会会長としてその保全活動を牽引。また、別府大学や総合地球環境学研究所の客員教授として持続的な地域開発に携わる研究者との交流を深めるほか、大分県教育委員として教育現場に、大分県農林水産研究指導センター研究指導顧問として研究現場に参画している。

撮影/甲田和久
松山 麻理(まつやま まり)
ブランドエディター/オイシックス・ラ・大地株式会社 らでぃっしゅぼーや通販事業本部 販売企画室
慶應義塾大学総合政策学部卒。オイシックス・ラ・大地社で、らでぃっしゅぼーやのブランド育成に従事。作り手と生活者を繋ぐ季刊誌『おはなしSalad』の企画・編集、ブランドサイトの企画・コピーライト・編集などを中心に、サステナブルな取り組みを発信する。

フードロス削減プロジェクト「ふぞろいRadish」及びサーキュラーエコノミー推進プロジェクト「ぐるぐるRadish」のコンセプト立案・販促プラン・ブランディングを担う。「規格外」をテーマに産地と協力して、「ふぞろいパール」や「ふぞろいちりめんつ」、「ふぞろいセロリの野菜だし」など素材の個性を楽しむ商品開発にも携わる。「ふぞろいRadish」でジャパン・サステナブルシーフードアワード2021ファイナリスト表彰。「ぐるぐるRadish」でcrQlr Awards 2022「捨てない循環デザイン賞」受賞。
[お問い合わせ]
国際交流基金(JF)
国際対話部 事業第1チーム
電話:03-5369-6072
Eメール:gp1_info@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください。)
